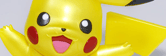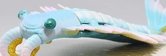↓
▼生き物ガチャ・ミニフィギュア レビュー
-
■あそべる生物フィギュアシリーズ/カプセルアニア他コンプした弾レビュー
▼コンテンツ
 |
■タカラトミーアーツ あそべる生物フィギュアシリーズ 昆虫の森 でたぞ!4大昆虫  タカラトミーアーツより2025年6月発売の一回300円ガチャ。 夏の風物詩「昆虫の森」ガチャシリーズが今年もやってきた!  ラインナップは「アトラスオオカブト」、「ミヤマクワガタ」、「シロスジカミキリ」、「ナナホシテントウ」の全4種。 本体サイズは4.8センチ~10センチのたっぷりボリュームとなっている。 前年までの200円から惜しくも300円に値上がりしているが・・・ まずこのご時世に今年も無事最新弾を重ねられた事を祝おうではないか!!  と言う事で中身を見ていくぞよ。 まずは新登場の「アトラスオオカブト」 カルコソマなのに潔い黒一色・・・ッ!! そして脚が短いのは、 実は一部パーツのみ新規となるリデコアイテムだから使いまわしの都合であるぞよよよよ・・・。   胸角はかなり内に巻いており独特のシルエット。 ひょっとしたら温めて広げるともう少し綺麗になったかもしれないがまぁいいでしょう! 2017年、2018年、2019年、2021年弾には同じカルコソマ属のコーカサスオオカブトが入っていたが、 胸角の具合を見るにちゃんと別造形っぽいぞよ。  続いて過去弾で幾度も登場している「ミヤマクワガタ」 2016年弾では前翅が合金パーツだったようだが、本弾では普通に本体と同じ素材ぞよ。 2017、2021弾にもラインナップされており、たぶん原型は流用されていると思われる。 ・・・が、先行予約時は「全て新規金型」と宣伝されていたのでそっくりなだけで別造形なのかもしれない・・・。   アトラスもミヤマもどっちも展足ポーズぞよ。  前年までは200円だったので無彩色でも納得感あったけど、300円となるとちょっと話は変わってくる! 今回はややハズレっぽい感が否めないぞよよよよ・・・。  造形はリアル調でめちゃくちゃ悪い訳ではないけど良い訳でもない。 「あそべる生物フィギュア」の中ではやや物足りないと言わざるを得ないだろう・・・!  と言うかこの2025年、明らかに「あそべる生物フィギュア」がトーンダウンしていると感じるぞよよ! 今年のラインナップを振り返ってみると、 3月の「みずべのなかま 自然にあつまれ!」は総集編弾で新規造形無し。 4月の「ガチャアクション THE恐竜 太古の支配者」の完全新規はディメトロドンのみ。 そして6月の本弾・・・とそもそも3タイトルしか出てないんですね! 去年は6月までに5タイトルでており、新規造形も豊富だった事を考えると縮小傾向にある。 こりゃどう考えても物価高や諸々の情勢不安が影響しているとしか思えんぞよよよよ・・・。  な~んか他メーカーも元気ない気がするぞよね~・・・。 最近生き物ガチャはどこも勢いが凄かったし、今年は充電期間と言う事かな~。  「昆虫の森 怪音波のなぞ(2024年5月)」に入っていたカブトムシとアトラスを比べてみると・・・ 胸と頭以外共通パーツっぽいぞよ。  同ギラファノコギリクワガタと本弾ミヤマもやはり脚や腹部が共通パーツのリデコである。  続いてこちらは新規造形の「シロスジカミキリ」! 本弾では最も彩色箇所が多い豪華なアタリ枠だ! 背中側の色数も多ければお腹側もばっちり色がついており、 各部ディテールには白っぽいスミイレが施され情報量アップが図られている。 300円でこれは嬉しい仕上がりぞよ!!  鞘翅目カミキリムシ科のうち、国内のフトカミキリ亜科の中では最大種となるシロスジカミキリ。 全長は4.4~5.5センチほど、触角はオスの方が長く、第7節端~8節の辺りで翅を優に越し、 メスはやや短く10節辺で少し超える程度になるぞよ。 ブナ科の生木を寄主としており、 もともと雑木林のコナラやクヌギなどを加害していたが、おろかなにんげんどもが森を切り開き、 クリの木を植えるようになるとこれが口にあったようで盛んに食うのでクリ農家さんには大いに嫌われている。 成虫は他に広葉樹の樹液なども好物であると言うぞよ。 大体夏頃に出現して夜に活発に動き、交尾を済ませるとメスは生木の低い所を円形に齧って穴を開け産卵。 孵化した幼虫は樹皮下に潜み3~4年もかけて中を食い進んでいくので寄主とされた木は弱ってしまうぞよ。 おろかなにんげんどもの植えた木を食害し、またこれによって折れた樹で怪我をする人も出るので困った奴だが、 一方では雑木林の新陳代謝を促す存在でもあり、成虫が齧った穴からは樹液が溢れ、 カブトムシやクワガタなどはこれを目当てに集まってくる。 おろかなにんげんどもにとっては厄介者だが、自然には無くてはならないサイクルの一部なのだ。  シロスジカミキリは全体に粉を吹いたような色をして、黄色と白の斑紋を纏っているが、 死ぬとたちまち退色して白んでしまうぞよ。 「シロスジカミキリ」の名前はこの死んだ状態に基づくようである。 大きな特徴の一つには鳴き声もあって、シロスジカミキリはヤスリ状になった翅の付け根と前胸の後ろを擦り合わせて、 ギュイギュイギュイ・・・ゴシゴシゴシ・・・とゼンマイ玩具みたいな摩擦音を発するのだ。 おろかなにんげんどもが背中をひょいっと持ったりするとこの音を発する事から、 恐らく威嚇音であると思われるが・・・効果の程は定かでないぞよ。  ラストはこちらも新規造形の「ナナホシテントウ」! 鞘翅目テントウムシ科の中でも日本では最もポピュラーに見られる普通種でお馴染みのテントウムシぞよね! 実物の大きさは5~9ミリ程度でごく小さいが、真っ赤な円盤型の体に七つの黒点が浮かび良く目立つぞよ。 胸にある白い模様が目に見える事も特徴である。 テントウムシは可愛いからと言ってつんつんしたりすると、脚の関節から黄色い体液を出して警告してくるぞよ。 アルカロイドを含むこの液はおろかなにんげんどもには微量であまり良く感じられないが、 鳥類からは激烈に危険な匂いがするらしく、鳥はテントウムシを食おうとしない。 この匂い攻撃は幼虫の頃から備わるナナホシテントウの防御技であるぞよ。  ナナホシテントウは肉食で食欲旺盛。 農作物を食害する厄介なアブラムシ類をよく食ってくれる為に益虫としても知られているぞよ。 害虫となるアブラムシに対して農薬を使わず、 天敵であるテントウムシを放って対抗する作戦を生物農薬による天敵農法などと呼ぶ。 おろかなにんげんどもが農作物を育てるようになってから様々な方法が試みられたが、 これは自然の力を借りているようで一見すると理にかなっており良さそうな考え方だ・・・が、 まず大体の場合は上手くいかないぞよ。 とにかく農薬を使わないと害虫と言うのは夥しく出現するんですね。 それを食う天敵虫が繁栄し、うっかり逃げ出して広域に拡散したりすると自然のサイクルが崩れて 何かとんでもないことが起こらんとも限らないぞよ。 世間では無農薬だとかオーガニック野菜だとかがもてはやされるが、 わたくしはきちんと適切に薬で処理されている野菜の方が断然安心できるぞよ!!  日本で見られるお馴染みの昆虫が新規造形ラインナップ! どちらも彩色が凝っているアタリ枠ぞよ! どうもネットの通販サイトでは本弾は均一アソートでないとし、ナナホシテントウを抜いたセットを販売しているものがある。 ・・・と言う事でひょっとしたらナナホシテントウは数が少なくプチレア枠? ・・・かもしれない・・・。  シロスジカミキリはかつては普通種としてその辺で見る事が出来たが、 生息環境の変化によって近年ではあまり見かける事の無い種となってきている。 一方で同じカミキリムシの仲間では、 昨今外来の凶悪なカミキリムシ達が跳梁し、街路樹を食害して人々を困らせているぞよ。  ナナホシテントウは国内では特に絶滅の恐れも無いごく普通種であるが、 先にも申した通りおろかなにんげんどもはこのようなテントウムシを生物農薬として安易に導入しがちであるぞよ。 ナナホシテントウもアブラムシ駆除の目的で北アメリカに放たれた事があったが、 案の定持ち前の拡散力と食欲を武器に在来種を駆逐しながら暴走・増殖していると言う。 ちっちゃくて可愛い姿とは裏腹になかなか狂暴な奴らなのだ・・・!!  今回の弾では豪華仕様のこの二体を引きたいところぞよね・・・!  ちなみにタカラトミーアーツの公式Twitterで台紙ビジュアルが先行公開された時は シロスジカミキリの模様が製品と異なっていました。 実物の方がより彩色箇所が多く豪華になっているぞよね!? これが300円パワーと言う事か・・・!!  「あそべる生物フィギュア」は一部可動のぷちアクションフィギュアシリーズ。 アトラスオオカブトは前翅が開閉し、  前脚もスイング可動するぞよ。 パーツが微妙に抜けやすい気がするので、 脱落が心配な時は木工ボンドなどで軸を太らせるのがお手軽ぞ。  ミヤマクワガタは大顎と前翅の開閉、足がスイングとなっている。  胸と腹も軸ぶっさしでちょこっとロールしなくも無いが、 すぐにすっぽ抜けてしまう。  シロスジカミキリは触角が後ろを向いており、脚も整えられているので明らかに展足ポーズである。 つまり、死体の姿と言う事。 カミキリムシはご覧の通り触角がごく長いので、前を向けて標本を作ると標本箱の中で倍のスペースを食ってしまう。 また、繊細な部位が外に飛び出していると破損の危険も増えるぞよ。 従って長い触覚は後ろ側に流して省スペースを図ると言う訳。 しかし本商品は死後退色する前の黄色い彩色をしているので、触角を前や横に開いた活き活きしたポーズで飾りたいところ・・・  と思ったら付け根がボールジョイントになっていてちゃんと前に向けると言うね! こちらも前脚が可動しシルエットを変える事が出来る。  そればかりでなく・・・やはり前翅が展開可能となっており、飛行形態にもモードチェンジ可能ぞよ! 通常時は見えない腹部もきちんと彩色されており、キモ可愛い。  と言う事でなかなかツボをついたギミックなのです。  国内最大種であるシロスジカミキリはその大きな体になかなかの飛翔能力を備えており、 夜は灯火などにやってきておろかなにんげんどもを驚かせている。 なにせ触角がごく長いので、その存在感は本体全長の二倍くらいあるから迫力満点ぞよ。  こんなでっけーのが夜に飛んで来たらびっくりしちゃうぞよね!? 本当は前翅はもっと上に跳ね上げたいところですが・・・一軸スイングなので横にしか開かないのはご愛敬。  ナナホシテントウは前翅が開閉する。 隠れて見えない腹部もばっちり彩色! 四角い模様がプリントされているけど、これはリアルなんですかね? どちらかと言うと全体に黒で左右脇がオレンジってイメージだが、 こういうプリントをするからには何らかの資料を見てパターンを作っていそうであるぞよ。  ぶーん。 ちなみに毎度のことですが翅は展開ギミックのみで後翅は付属しない。 本来ある筈の後翅は脳内で羽ばたいている風に想像しイメージで補いながらごっこ遊びするのが良いでしょう! 昆虫の翅はごく超スピードで羽ばたいており、肉眼ではっきりとその姿を捉えるのは難しいからして、 玩具造形でもやはり「見えない」のだ。  ただ、もともと食玩シリーズだった「昆虫の森」、過去弾では後翅パーツが付属した時期もあったぞよ。 今回300円に値上がりしたし・・・なんとか後翅パーツ、おまけで入れてもらう事って出来ませんかね~? タカトミアーツ~! わたくしとお主の仲じゃないか~! もうちょびっとだけサービスしてくれぞよ~っ!!  この2025年は不思議とカルコソマの玩具が集中して発売していたぞよ。 左が本商品、真ん中はバンダイ迫真のリアル造形「いきもの大図鑑アドバンス コーカサスオオカブト(2025年4月)」 右が本家タカトミの「アニア AL-18 アトラスオオカブト(2025年4月)」だ。 この中だと本商品が最も安く、最も忠実でない・・・と言う事になってしまうぞよ。 ま~そこは300円なんでね! わたくしに免じて許してやってほしいぞよよ!!  リデコカブクワで相撲対決だッ!! のこったのこったぞよーっ!!  シロスジカミキリはルッタの乗り物にも丁度良いサイズ感。  ナナホシテントウさんも乗り心地が良さそうだ。 お~い、乗せてくれぞよ~!  小さすぎて飛べなかったのでカートとして遊ぶぞよ! なかなか可愛い新入りではないか~。  毎年恒例の「昆虫の森」シリーズ! 今回は300円に値上がりと言う事で、アタリ枠は従来の昆虫に比べても色数が多く豪華になっている! 特にでっかいシロスジカミキリは是非ともゲットして欲しいですよ~。  「昆虫の森」2025年弾でした! 夏の風物詩として我々を楽しませてくれるタカトミアーツの長寿シリーズ。 今年もゲットぞよ~!!  夏休みのお供に「ばらむツ怪奇倶楽部」もよろしくぞよ! :このリンクを踏んで何かポチるとわたくしにささやかな報酬が入りサイトの運営費となるのでよろしくぞ! ・「シロスジカミキリ フィギュア 15CM級 完成品 機械改造」 ・「学研の科学 恐竜化石発掘キット」 ▲TOP |
■いきもん サイエンステクニカラードイツ箱 マグネットコレクション4  株式会社いきもんより、2025年5月19日発売の一回500円ガチャ。 科学、物理、生物学などあらゆる理系分野をテーマにしたガチャシリーズ「サイエンステクニカラー」のうち、 標本箱をモチーフとしたマグネットシリーズ、「ドイツ箱マグネットコレクション」の第四弾ぞよ!  従来はドイツ箱風のケースに紙製ダイカット仕様の鱗翅目達が入っていましたが、 この第四弾はシリーズで初めて甲虫を特集し、更に全ラインナップ立体仕様のフィギュアが封入されている豪華仕様となっている! ラインナップは「ヤマトタマムシ」、「オオルリオサムシ」、「ショーエンヘルホウセキゾウムシ」、 そして「オオセンチコガネ」が緑、赤、青の三色収録された全六種! このうちオオセンチコガネ各色は均一アソートでないっぽくレア枠であるぞよ。  リーフレットは各ラインナップ専用のものが付属。 いきもんでは毎度おなじみの仕様ぞよね! これも集めたくなる嬉しいおまけぞよ。 ガチャを開封したらリーフレットやミニブックは捨てちゃうっておろかなにんげんが大半でしょうが・・・ 勿体ない事です! わたくしは畳んで写真ファイルやカードファイルにコレクションしているぞよ~。  まずは鞘翅目タマムシ科の「ヤマトタマムシ」、 タマムシの中のタマムシにしてその美しい姿からこの日本では縁起物として親しまれ、 装飾品や工芸品に利用されるなど文化的にも関わりが深い昆虫ぞよね! 最大の特徴は緑に光る金属光沢の輝きぞよ! 「フタスジアオタマムシ」とか「フタスジルリタマムシ」とか呼ばれるように、背中に赤の縦じまが入る事も特徴の一つである。 この金属光沢は多層膜干渉による構造色であるぞよ。 つまり、透明な極めて薄い膜が何層にも重なって、 膜と膜の間に構成する物質の違いや成分の違いによって幾層もの界面が生じ、 透過する光がそれぞれの界面で反射を起こし、互いに干渉する事によって特定の波長だけが強調され、 我々の目に色として映る・・・こういう仕組みなワケです! ヤマトタマムシの場合は黒色色素・メラニンを含む層と含まない層とが交互に積層されており、 入射した光がそれぞれの界面で反射光となって、膜の厚みの二倍の位相差を持った光の相互作用が、 波長のやや短い緑や波長の短い青として角度依存性を帯びて見えるのだ。 こうした構造色の輝きはフィギュア彩色の原理ではまず再現できないので、 大体の場合メタリック彩色で表現されるが、本商品も同様である。  中身のフィギュアは玩具っぽいが、 あくまで「ドイツ箱に入った標本」全体としての印象を表現しているのであるのだからまずまずと言ったところだろう。 わたくしがこの商品を初めに見て不思議に思ったのは・・・脚がちゃんと細い!! 明らかにフィギュアで再現できない繊細さ! 触角は玩具然として太いのに、こりゃどうやってるんだ? と思ったらなんと立体は上面のみで、脚は浮き出した台紙にプリントで再現されているのだ・・・! このアイディアのお陰でやや玩具然としながらも、 標本箱に入った1/1サイズ昆虫としての実在感がぐ~んと高まっていると言う訳! これはよく考えたものぞよね・・・!!  続いて「オオルリオサムシ」 この弾は珍しい昆虫の玩具化ばかりで見所があるぞよ!  鞘翅目オサムシ科のなかでもオオルリオサムシは北海道だけに分布する日本固有種。 多くのオサムシは飛翔性を失っている為広範囲に移動できず、地域性が生まれて多様な変異を遂げており、 オオルリオサムシの場合は金属光沢を示し、 また地域によって緑から赤っぽいものまで不思議と色が違う事で知られているぞよ。 亜種内での地域変異はいくつかの型に分けられ収集の人気対象になっており、コレクターも多い。 広い山中に隠れ住むほんの2~3センチ程のオサムシを目で見つけるって事はちょっと難しい。 それじゃあどうやって採るのかと言えば、罠を仕掛けるのである。 100均とかに売ってるプラスチック製の使い捨てコップを地面に埋めとくと、 おっちょこちょいなオサムシはつるんと落ちて出られなくなっちゃう。 これを集めるのが傷つけずに済むし最も簡単な方法ぞよ。 ただ、現場へ二回足を運ばねばならない事と、コップを仕込んだ位置を覚えとかないといけないのがちょっと大変だ。 埋めたコップをそのままにしたら環境を汚染する事になってしまうので、絶対に回収しなくてはならないのだ。 そして他の虫もうじゃうじゃ入ってしまうぞよ。 時たまクワガタなんか入っていたら大当たりだ!  成型の都合で触角はかなり太いが、こちらも脚は立体台紙への印刷で繊細に出来ている。 オオルリオサムシはカタツムリ食で知られるマイマイカブリと近縁であり、やはりカタツムリが大好物。 幼虫の頃も成虫になってもカタツムリを捕食しており、これが飛翔性を失った事にも関係していると言われているぞよ。 飛んで広範囲の餌を探すより、 地面をちょこまか歩き回ってのろのろ動いているカタツムリを独占した方が有利だったと言うワケ。 プラコップに引っかかる一方でなかなか強かなヤツぞよね・・・!  続いて鞘翅目ゾウムシ科の「ショーエンヘルホウセキゾウムシ」! ニューギニア島で見られるゾウムシの仲間で、この種も地域によって多様な色彩を纏っているが、 これがまるで誰かに色でも塗られたのかと言う奇妙な姿をしているぞよ! 本商品は中でも美しいとされるインドネシア南西パプア州のソロン周辺の個体群をモチーフとしているようだ。  ホウセキゾウムシもまた構造色の輝きを纏うが、タマムシの多層膜干渉と違ってフォトニック結晶と言う構造を持つ。 これは垂直方向の繰り返しや水平方向の繰り返しと違う、立体構造による発色であるぞよ。 つまり、角度依存性を持たず、どこから見ても同じ色に見える。 このフォトニック結晶を帯びた昆虫は多くの場合緑、青、紫などに見える事が多い。 本種も正に青と緑のストライプぞよね! ホウセキゾウムシの場合は逆オパール型のフォトニック結晶によって発色しており、 一口にフォトニック結晶と言っても色々な構造があるぞよ。  ゾウムシはその名の通りゾウのように長く伸びた口吻が特徴的。 これは産卵の際に木や種子に穴をあける為に進化してきたものであるぞよ。 身近な害虫から世界の奇虫まで様々知られているが、中にはとんでもないシルエットのヘンテコな奴もいるぞよ。 甲虫の中でも特に多様なグループなので種ごとの生態や詳しい事はよく解らない事が多いのだ。  5.5センチのドイツ箱の中に1/1スケールの昆虫が入っています。 過去弾では横置きだったけど今回は中身の都合で縦置きになっている。 ドイツ箱と言うのは標本箱の通称であるぞよ。 なんでドイツ箱と言うのか良く判らんけど、たぶんドイツの標本商か博物館で使われていたのが元なんだろう。 密閉性に優れ、ガラス蓋がついて中身が覗けるようになっている。 普通標本箱は容器と蓋が遂になっていて、同じ型の標本箱でも蓋を交換できないくらいぴったり密閉されているぞよ。 ほんの隙間でも空いているとカツオブシムシなんかの害虫が目敏くやってきて中身を食っちゃうので、 それは厳重なのである。 標本箱は大体木で出来ているので、歪みがあったり湿気やなんか収縮したりもする。 だから容器と蓋をそれ専用に作って、僅かな歪みも計算してピッタリ合うようにきっちり作ってあるのだ。  標本箱の中にはちゃんとラベルもついています。 昆虫標本を作る上ではラベルが重要であるぞよ。 ラベルにはそれが何の種でどこでいつ採集したものかを記してある。 昆虫標本は大事に保管すれば数百年も保存できるワケだけど、 中にはその間に絶滅してしまう個体群もいる。 そんな時、その昆虫がどこでいつ採集されたか標本と共に伝わっていれば、 生物を研究するうえで重要な情報になると言う訳。 昆虫標本においてはラベルこそがその真価であるとも言えるのだ。 こんな風に箱につけといても良いし、標本と一緒にピンに刺してとめておいても良い。 これがしかし、人気の種であると嘘ついて価値を釣り上げる奴もいるから厄介だ。 ヘラクレスオオカブトとかニジイロクワガタなんかは飼育が容易になって広く出回った為に、 もう滅茶苦茶のまぜこぜになってラベルも当てにならないぞよ。  裏面はマグネット仕様になっています。 冷蔵庫やデスクに貼り付けて遊べる嬉しい仕様ぞよね!  ラストは「オオセンチコガネ」! 鞘翅目センチコガネ科の金属光沢が美しい甲虫で、うんちを食べる所謂糞虫であるぞよ。 やはり地域性の変異が多様であり、本商品でも三色ラインナップされている。 こちらは緑バージョンだ。  北海道から九州まで普通に見られるオオセンチコガネは牛や馬、鹿などの大型哺乳類の糞に集まり、 これを食しまた子育てに利用する糞虫であるぞよ。 その身にまとった美しい金属光沢の輝きはやはり多層膜干渉による構造色である。 こんな風に緑になるのは「ミドリセンチコガネ」と呼ばれており、 京都周辺で多く見られる基本の色の一つである。 色彩変異に富んだオオセンチコガネはこの緑を含め、赤、青の三つの型が知られており、 稀にはその中間の色も現れる事から、コレクターはこいつらでグラデーションを作ってやろうと 標本箱いっぱいに色違いを集める事を夢にしているのだ。  続いてこっちは赤バージョン。 赤緑とか赤銅色のオオセンチコガネは最も一般的なカラーと言われているぞよ。 和名に含まれる「センチ」とはトイレの古語「雪隠」に由来し、古くからうんちに集まる虫である事が知られていた。 成虫は大型動物の糞を好み、秋の産卵期になるとメスは糞の下に穴を掘り糞を埋めると、 その中に産卵し、産まれた幼虫もやはり糞を食べて成長する・・・と聞くとなんだかばっちい虫のようだが、 このような糞虫が動物の糞を処理してくれるからこそ自然が美しく保たれる、 言わば自然の掃除屋さんなのである。 近頃はマタギのような人がいなくなり、誰も動物を狩らなくなったので日本中で鹿が大量発生して問題となっているが、 これに便乗してオオセンチコガネも数を増やしていると言うぞよ。  地域によって様々な色を纏うオオセンチコガネであるが、なんで色の違いが現れるのかはっきりとした事は謎であるぞよ。 一つ言えることは遺伝的要因によるものではないと言う事だ。 近畿地方では赤、緑、青全ての変異が見られるが、 それらの集団は必ずしも遺伝的系統で色分けされている訳では無かったぞよ。 甲虫の前翅はタンパク質とキチン質を主成分とするクチクラからなる。 オオセンチコガネは外表皮部分にある多層構造が光を反射して構造色を示すが、 赤、緑、青の各オオセンチコガネではこの厚みが微妙に異なる為に違った色に見えるのだ。 ではどうして地域によって多層構造の厚みに違いが出るのか、これがよくわからなくて不思議なんですね!  脚はやはり立体構造にプリントで再現されており、実に繊細であるぞよ。 胸の辺りも印刷されていて実在感を高めている。 言わばトリックアート的な仕組みぞよね! こりゃ面白いアイテムです。  最後はオオセンチコガネの青バージョン! 所謂「ルリセンチコガネ」と言う奴で、奈良、和歌山、三重県辺りで見られる珍しい型であるぞよ。 奈良で最も多く見られると言う事は、こりゃやはり鹿の集団やそのうんちと何か関係していると思われる。 愛好家も多く、割と身近な虫であるのに未だ解明されない事が多いとは、 うんちを食う以上累代飼育が難しい点も上げられるぞよ。 何せ幼虫を飼うには動物のうんちが必要であるからして、一般のご家庭で飼うのはちょっと難しい。 オオセンチコガネを飼うには鹿も一緒に飼わなきゃならん。 そればかりでなく、ひょっとしてうんちの違いで色が変わるのでは・・・? と言う事を調べるには多種多様な新鮮なうんちを集める必要がある。 こりゃなかなか難しい事ですぞよ~。  糞虫はうんちを食べているので、標本もそれはうんち臭がする。 清潔に保つには捕らえてきた虫を暫く飼って糞抜きしなくちゃならんぞよ。 容器に入れてしばらく水だけで飼うとか、昆虫ゼリーを与えて中身が入れ替わるのを待つとか、 方法は様々だが、とにかく食ったうんちを外に出さなきゃならん。 これを怠ると標本になってからもず~っとうんち臭がするから大変なんですね! そこんとこ言えば玩具は清潔無臭で楽しめるのがありがたいポイントぞよ。  オオセンチコガネの基本の型三色がフルラインナップ! どうやらこれらは他の虫と均一アソートでなく、数が少ないみたいぞよ。 ひょっとして1/3しか入っていないとか・・・? ネット通販やオークションでは他のアソートの2~3倍価格で取引されており、レア枠のようだ。  本物の虫よりお高いじゃないか~っ! 色彩バリエーションに富む虫と言う事で今後のカラバリ再録もあり得そう。 なんならオオセンチコガネだけの特集弾とかも出来そうぞよ。  重ねるとまるで博物館の標本箱のような趣。 中身の虫は結構玩具然としているんだけど、 足が繊細なのでぱっと見本物と見紛うような実在感があるぞよ。  他の玩具と組み合わせて博物館遊びも出来ちゃうね! スケールを気にしなければジオラマ背景に使っても良さそうだ。  各標本箱はマグネット仕様なので金属にぺたんとくっつけて飾る事が出来ます。 磁力は強くもなく弱くもなくほどほどぞよ。  憧れの標本箱が玩具になった・・・! シリーズ初の立体造形となった「ドイツ箱マグネットコレクション」でした! このシリーズは人気があってあっと言う間に売り切れちゃう。 今回は立体仕様と言う事で特に注目弾となっている。 見つけたら即ゲットをおすすめするぞよ!  本商品は「ぞよちゃんねる」の動画レビューでも紹介しているのでこちらも参照のことぞ!  全く関係ないが無料で遊べる「ばらむツ怪奇倶楽部」もよろしくぞよ!! :このリンクを踏んで何かポチるとわたくしにささやかな報酬が入りサイトの運営費となるのでよろしくぞ! ・「クレイモデルキット ウンコスルデイズ あにまるうんちセット1 ねこ&くま+サラリーマンうんこ」 ・「池田工業社 無限うんち製造機」 ▲TOP |
■タカラトミーアーツ あそべる生物フィギュアシリーズ ガチャアクション THE恐竜 太古の支配者  タカラトミーアーツより2025年4月発売の一回300円ガチャ! 大人気「THE恐竜」シリーズの2025年春弾ぞよね!  ラインナップは「ケラトサウルス」、「テリジノサウルス」、「ディメトロドン」、「アルゼンチノサウルス」の全4種。 本体サイズ12・5~16センチのビッグサイズフィギュアぞよ!  それでは中身を見ていこう・・・まずはこちら、「ディメトロドン」ぞよ! いきなり恐竜じゃない古生物ですが・・・ 本弾中唯一の完全新規造形(たぶん)の目玉ラインナップとなっている!!  ディメトロドンは約2億9500万年~2億7200万年前の前期ペルム紀、現在の北米に生息したとされる単弓類。 見た感じ恐竜然として、玩具などでは恐竜と混じってラインナップされる事の多いディメトロドンだが、 中期ペルム紀にはすっかり絶滅しているぞよ。 恐竜が出現するのは2億3000万年前の三畳紀くらいだと思われるので、 ディメトロドンは恐竜よりずっと古い古生物、と言う事になる!  その昔は哺乳類も爬虫類から進化してきたものと考えられていた。 ディメトロドンのような単弓類を哺乳類型爬虫類などと呼んで、哺乳類の特徴を持った爬虫類の一種と位置付けていたぞよ。 しかし近年の研究ではどうやら哺乳類と爬虫類は別々のルートで進化してきたことが判り始めた。 我々哺乳類は単弓類から獣弓類を経て進化してきた動物達。 頭骨の目の穴の後ろに一つ穴が開いているから単弓類ってワケぞよ。 そして爬虫類は双弓類と言う別のグループから進化してきた動物達。 頭骨に二つ穴が開いているから双弓類と言うワケぞ。 二つは有羊膜類から枝分かれした姉妹群ってワケぞよね! と言う事でこんな恐竜然としたディメトロドンですが、恐竜とは全然関係なく、 むしろ我々哺乳類と非常に近縁な、遠いご先祖様と言った方が良い古生物なのだ。  なんと言っても最大の特徴は背中の大きな帆。 これは体温調節の役割を持っていたとされる事もあるが、単弓類には短い帆の種も多く、 また血管があまり通っていない事からも、体温調節に利用出来たと言う説はどうも信憑性に欠け、 現在ではあまり支持されていない。 やはり体を大きく見せて相手を驚かせたり、求愛の為に発達したディスプレイだったみたいぞよ。 普段は寝そべり態勢で四足歩行をしたが、時には二足歩行で立ち上がって移動する事も出来たと言う。 多くの種では体長1.7~4.6メートル程だったとされ、肉食傾向にあり当時の頂点捕食者の一つであった。 一方でほんの60センチくらいの小さい奴もおり、現在までに20種くらいが命名されている。  続いてこちらは正真正銘の恐竜だ! 後期白亜紀、アルゼンチンに生息したとされる超巨大竜脚類「アルゼンチノサウルス」! 陸上では最大級とされるティタノサウルス類の一種であり、推定全長30~36メートルに達したとされるが・・・ 発見されているのは脊椎骨、脛骨、ごく不完全な肋骨、仙骨の一部のみであり、 肝心の首と尾がさっぱり不明であるぞよ。 従って推定全長にも具体的な証拠がなく、小型の近縁種を発見部位に合わせてスケールアップした姿から導き出されたものに過ぎない。 ともかくデカい事は間違いないが、アルゼンチノサウルスは全貌の良くわからない竜脚類なのだ。  「THE恐竜」シリーズでは初登場となるアルゼンチノサウルス。 生体復元では首がぶっとい巨大竜脚類として描かれる事が多いが・・・ 本商品ではいかにもスタンダードな竜脚類のシルエットぞよね! こりゃどうやら「ガチャアクション THE恐竜 地球ギガバトル!(2020年12月)」に収録された竜脚類、 「スーパーサウルス」のリデコアイテムみたいぞよ! 元は青かった体が今回はオレンジになり、スーパーサウルスにあった頭の可動域が削られている事から、 一応頭部は新規造形みたいぞよ。  後期ジュラ紀の竜脚類・スーパーサウルスはディプロドクス科。 アルゼンチノサウルスはより進化型の竜脚類であるティタノサウルス科であるぞよ。 白亜紀の中頃にディプロドクス科やブラキオサウルス科が絶滅すると、 それと入れ替わるようにティタノサウルス類が勢力を拡大。 そのニッチを埋めるように取って代わったと考えられている。 本商品でも首を挿げ替えられて取って代わられてしまったと言うワケだ・・・!  スーパーサウルスも最大全長33~40メートルと推定される超巨大竜脚類であったと考えられているが、 こちらも部分的な化石から復元された姿なのでかなり盛られている筈ぞよ。 全貌が判然としない竜脚類の、それも玩具の復元となればぱっと見で何の種であるか判別する事は難しいからして、 スーパーサウルスをリデコでアルゼンチノサウルスにしても良いじゃないか~!  「ガチャアクション THE恐竜 地球ギガバトル!(2020年12月)」のラインナップは 「ケラトサウルス」、「テリジノサウルス」、「スーパーサウルス」の全3種だった。 アルゼンチノサウルスがスーパーサウルスのリデコである事を鑑みると、 本弾とラインナップが全て被っているぞよ。 つまり本弾はこの2020年12月弾の金型を引っ張り出して来たものと考えられ、 新たに新規造形ディメトロドンを加えた実質再販弾と言えるだろう!  「あそべる生物フィギュアシリーズ」は思いがけない動物達をリアル造形で収録する通なガチャシリーズだが、 不思議と「THE恐竜」は正確性に重きを置いておらず、原型の使いまわしが多くみられる。 恐らく「あそべる生物」では最も人気のあるカテゴリだと思われだけに、 この力の抜き様は奇妙な感もあるぞよ。  とは言え本弾のディメトロドンのように、新規造形枠は見所もある。 300円でビッグサイズ&彩色済みフィギュアを出す為にタカトミアーツも色々苦心していると言う事でしょう!  「あそべる生物」は各部可動のアクションフィギュア! ディメトロドンは口開閉、首、四肢、尾の二か所がボールジョイント接続で表情付けが可能となっている!  ずんぐり四肢には元気いっぱいの剽軽なポージングが似合うぞよね!  軸ロールを使えば尻尾を左右に振る事も出来るぞよ!  アルゼンチノサウルスは四肢、首三か所、尾の二か所が可動ポイント。 こちらもボールジョイントと軸ロールを上手く使えば大きくシルエットを変える事が出来る。  本家タカトミから発売されているアニアの竜脚類は脚が固定だが、 本商品はこの点において本家を上回る可動域を備える! のっしのっし歩くポーズを作っちゃおう!!  首の前後を入れ替えれば往年の鎌首をもたげたポージングも出来ますぞよ!! このシリーズにおいては少々の破綻は気にせず、 分割をダイナミックに利用する事が上手なポージングのコツなのだ!  前脚は軸が長めに設けられているので開いたり閉じたり色気のあるポージングも可能だ。 300円にして正に「あそべる」仕様と言うワケぞよ・・・!  続いてこちらは「テリジノサウルス」! 近頃映画やゲームへの登場によって知名度・人気を高めている後期白亜紀の竜盤類獣脚類恐竜ぞよね! 発達した腕に備えた鎌のような爪から、「刈り取る者」の意を与えられたこの恐竜は、 見ての通り大鎌使いの凶悪な肉食恐竜・・・! ・・・ではなく、雑食性、あるいは植物食の大人しい恐竜だったと考えられているぞよ。  基盤的なテリジノサウルス類に原始的な羽毛の痕跡が見られる事から、 テリジノサウルスは羽毛恐竜として復元される事が一般的であるぞよ。 しかし本商品では珍しく全身すっかり鱗で覆われており、どこにも羽毛が生えていない。 そしてまた、テリジノサウルスは四本指を接地して歩いていたと考えられているが、 本商品では四本目の指が退化し、名残が見られるばかり。 普通の獣脚類的な足をしている。 これらは本シリーズの製品仕様が深く関わっているが後述であるぞよ。  前述の通り、テリジノサウルスは過去弾からの再ラインナップ枠。 「THE恐竜」においては「地球ギガバトル!(2020年12月)」ぶりの再録となっており、 茶色カラーからグレーに変更されている他、元は瞳の描かれていた目が金目に変更されているぞよ。 この金目仕様、シリーズではお馴染みなのだが、 前弾「海をゆく影(2024年6月)」では全ラインナップ黒目で統一されていたので久々の復活。 本弾では黒目二種と金目二種で半分ずつに分けられている。  ラストはこちら! ジュラ紀中期~後期まで長く繁栄した竜盤類獣脚類恐竜の「ケラトサウルス」ぞよ! 角を持つトカゲの意を冠された中型肉食恐竜で、その名の通り鼻の上にあるケラチン質の角がチャームポイント。 目の上にも一対の角がついていたとされ、本商品でもばっちり再現されているぞよね!  一応「ジュラシック・パーク3」の登場恐竜で、 最近では「ジュラシック・ワールド」のアニメシリーズでも度々登場していたが、 いつもちょいキャラなのでマイナーな感が否めない哀れなヤツぞよ!  下から見ると・・・おや・・・? 何か見覚えがある形ぞよね・・・おろかなにんげんどもも薄々気づいていると思うが、まず後述としよう!  ケラトサウルスも「THE恐竜 地球ギガバトル!」からの再録枠。 この二体は同じ弾からの復刻と言うワケぞよ!  どちらも金目仕様の格好良い仕上がり。 背中側が濃い色でグラデ彩色されており、見栄えがするぞよ。  余談ですが今回から背景紙を新しくしました! 長らく横着してぼろぼろのグラデーションペーパーを使い続けていたのですが・・・ ひょっとして10年近く使ってないか?と思い立ち、重い腰を上げて新調したぞよ。 背景紙って何選んで良いのかわからな過ぎて、最もシンプルな白背景にしたのですが・・・ お~っ! 編集が楽チンでこりゃ便利ではないか~っ! と言う事で今後は白背景で撮ってゆくぞよ! と言ってもグラデーション背景で撮ったストックがまだまだあるのですが。  おしり。 シルエットを大きく変えてごまかしているが・・・な~んかこの二体そっくりぞよね!?  と、本シリーズの秘密を暴く前に可動域を見ていこう! テリジノサウルスは口開閉の他、 首が二か所、足、尾の付け根が可動仕様となっており、動きを付ける事が出来るぞよ。  テリジノサウルスと言えば鎌のような長い爪が最大の特徴であるが、 本商品では残念ながら腕は非可動となっているぞよ。 この大鎌の用途は未だ謎に包まれており、 ひょっとして凄まじい威力を秘めた武器であったのではないか?と考えられた事もあったが、 日本の恐竜研究において意外な事実が判明している。 北海道で見つかったテリジノサウルス類「パラリテリジノサウルス」の末節骨を調べたところ、 爪の可動域はごく狭く、伝わる力も弱かった可能性が示唆されたのだ。 これではとても武器として使う事は出来なかっただろう。 テリジノサウルスが植物食であった事を鑑みると、 どうやらこの長い爪は熊手のような役割をして、 木の枝に引っかけて手繰り寄せるなどの用途で利用されていたみたいなのだ。  映画「ジュラシック・ワールド 新たなる支配者」の中では あのギガノトサウルスの腹を貫く程の威力を見せたテリジノサウルスの爪! しかし現実にはこんな使い方は勿論出来なかったに違いない! と言うか、おろかなにんげん! 君に鎌のような長い爪がついていたとして、 それで同じくらいの体格の動物の皮膚や硬い筋肉を突き破り、胴体を貫通させる事が出来るだろうか? こりゃどう考えても出来んぞよね! いかに太古の支配者・恐竜と言えども、そんなハチャメチャにバイオレンスな攻撃はとても出来ないのである。 テリジノサウルスの必殺攻撃は、だから映画の中だけのフィクションぞよ。  ケラトサウルスは口の開閉に加えて、 首、足の付け根、尾が二か所で可動し表情付けする事が出来るぞよ。  簡易可動ギミックだけど、工夫する事で活き活きとしたポージングを付ける事が出来るのだ! 300円にして実に「あそべる」仕様ではないか~っ!  勇猛なポーズが良く似合う! 脚の接地面が大きいので意外とポーズを付けても自立するぞよ。  タカラトミーより発売の本家アニアと並べて~。 ディメトロドンは「アニア ジュラシック・ワールド ディメトロドン(2022年7月)」として、 映画「ジュラシック・ワールド」に登場した姿で発売されているぞよ。 ジュラワ登場古生物は大胆にアレンジされている事が多いが、 ディメトロドンは概ねイメージ通りの造形だ。 本商品はアニアと比べても可動ポイントが多く、300円にしてアドバンテージがある。  アルゼンチノサウルスは「アニア AL-24 アルゼンチノサウルス(2024年3月)」として通年販売中。 こちらはアニア史上最も巨大なものの一つで、首がなが~く太いのもティタノサウルス類のスタンダードなイメージと言った趣。 可動面においては本商品の方が四肢が動くのが嬉しいポイントぞ。  アルゼンチノサウルスは本弾が初登場と言う事で、 わたくしはアニアのような首の太い新規造形竜脚類を期待していたぞよ。 「あそべる生物」は掌からはみ出す程の巨大生物がラインナップされる事もあるので、 ティタノサウルス類はこれまでにないサイズ感なのでは無いかと考えたのだ! しかし蓋を開けてみると過去弾のリデコアイテム・・・ サイズ感では去年のプレシオサウルスに負けていたのは残念な事です・・・! ま、なかなか可愛い竜脚類で彩色も綺麗なのでこれはこれでアリですが!  映画やゲームの影響で最近はティラノサウルスらに匹敵の人気があると言うテリジノサウルス! アニアでも古生物版、ジュラワ版両方で出ているぞよ。 写真真ん中が「アニア AA-06 決戦!恐竜大乱闘セット(2020年4月)」に収録された古生物版。 写真右が「アニア ジュラシック・ワールド 新恐竜たちの激闘セット(2022年7月)」で登場したジュラワ版。 ジュラワ版はこの4月に単品パケも発売されているぞよ。 解釈は異なるものの、アニアは両方とも羽毛の表現が見られるのに対し、 本商品では羽毛が一切生えていないのがかえって珍しいぞよ。  ケラトサウルスは映画のちょいキャラながら 「アニア ジュラシック・ワールド ケラトサウルス(2024年11月)」としてジュラワ版アニアが発売されたばかり。 この2024年11月発売分までのジュラワ版アニアは1200円。 2025年4月から開始される新パッケージには新たにカードのおまけがついて1300円となり、 従来のラインナップもリパッケージされているが、今のところケラトサウルスは漏れている。 ひょっとしたらリパッケージされず廃盤となる可能性もあるので欲しい人は早めのゲットをおすすめぞよ!  さて、おろかなにんげんどももお気づきの通り、 本シリーズ「THE恐竜」の、特に獣脚類はなんか全体的にシルエットが似ているぞよ。 試しにケラトサウルスと過去弾の「ギガノトサウルス」を並べてみると・・・ なんとびっくり! 頭と手以外造形が同じぞよ!!  なんなら本弾の獣脚類も胴体と脚が共通パーツじゃないか~っ! テリジノサウルスは尻尾を1パーツにして短くしているのが面白い工夫ぞよ。 と言う事で、どれもなんか微妙に正確でないのはパーツ共有の都合だったのです! この仕様はかえって面倒そうでどれだけコストカットされているのか謎ですが、 300円でデッカイ恐竜を沢山出してやろうと言う涙ぐましい努力が感じられるぞよよよよ・・・。  わちゃわちゃ集めよう、「THE恐竜!」 時代も生息域も異なるメンバーが一堂に会しているぞよ!!  うわーっ! いきなりケラトサウルスがアルゼンチノサウルスに喰らい付いた! ディメトロドンさん、逃げるぞよーっ!!  しかしそこへすかさず大鎌攻撃を繰り出すのはテリジノサウルスだ! わたくしは映画を見ながら「こんなバトルはでたらめぞよ!」と毎回憤っているが、 そんな事を言いつつ玩具で同じような事をしてしまうのがおたくの悲しい性なのです・・・!  ディメトロドンは恐竜ではないが、似たような帆のある恐竜には有名な「スピノサウルス」もいるぞよね! 「THE恐竜」においては「THE恐竜 3大恐竜登場(2023年4月)」で登場しているが、 こりゃどう見ても「ジュラパ3」のスピノサウルスぞよ! この夏公開される「ジュラシック・ワールド」最新作では、 いよいよ水棲に特化した復元の新スピノが登場すると言う事で、この夏もスピノの熱い年になりそうだ!  恐竜は主にアニアで集めているわたくし、「THE恐竜」はあんまり積極的に回してこなかったが、 それでもだんだん数が集まってきたぞよ! 今後もゆる~く集めていきたい次第。  と言う事で「THE恐竜」の2025年春弾でした! 今回は新規造形のディメトロドンが最大の見所ぞよね! わたくしはディメトロドンを含む単弓類の事をイマイチ知らないので、何か良い図録が欲しいと常々思っていたが・・・、 この冬の科博の特別展は「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」と題し、 地球史上5度にわたって訪れたと言う生物の大量絶滅が特集されると言うではないか! メインビジュアルにはディメトロドンも写っているので、きっと図録では詳細な解説も読めるに違いない! 実に楽しみな催しであるぞよ! おろかなにんげんどもも本弾のディメトロドンをゲットして、冬の特別展に備えようではないか!  竜脚類、ティタノサウルス類については「巨大恐竜展(2024)」レポや「ばらむツZ 8巻」も参照のことぞ! :このリンクを踏んで何かポチるとわたくしにささやかな報酬が入りサイトの運営費となるのでよろしくぞ! ・「シュライヒ(Schleich) ダイナソー ディメトロドン」 ・「アニア AA-03 最強恐竜対決セット」 ▲TOP |
■タカラトミーアーツ みずべのなかま  タカラトミーアーツより、2019年4月発売の一回300円ガチャ! 元祖「みずべのなかま」にして、 現在の「あそべる生物フィギュアシリーズ」に連なる知る人ぞ知る名作弾ぞよ!  なぜこのタイミングで紹介するかと言うと、 この2025年3月に「みずべのなかま」の総集編弾が出たばかりだからぞよ。 タカラトミーアーツから発売されていたギミック付き動物フィギュアは、 「あそべる生物フィギュアシリーズ」へと統合され現在まで続いており、 最新弾「みずべのなかま 自然にあつまれ!」では、 過去の「みずべのなかま」達が総登場しているが・・・ 残念無念ッ! 昨今の物価高に300円均一ではとても立ち向かえず、 元は豪華だった彩色が大胆にオミットされ、現行バージョンでは明るめのファンシーな単色仕上げとなってしまったぞよ。 今回紹介する元祖「みずべのなかま」は、これらの原型の初出にして、 最も豪華な彩色バージョンとなっている。  それでは中身を紹介いたそう・・・! まずはこちら「アメリカザリガニ」ぞよ! 本弾の目玉にして最も人気があった注目ラインナップだ!  これぞ身近なみずべのなかま・・・アメリカザリガニはちびっ子の玩具としてもお馴染みの動物ぞよね! その辺の用水やほんの水辺に必ずすみ着いており、 なんも考えずに生きているので動くものを見るやすぐに自慢の鋏で噛みついてくるので容易に捕まえる事が出来てしまう。 おろかなにんげんどもも幼少の頃にはザリガニ釣りをして遊んだ思い出がある事でしょう・・・!  元々はミシシッピ川流域を中心とした北米に広く分布する淡水生の甲殻類で、 日本では1927年頃にウシガエルの餌として持ち込まれたぞよ。 おろかなにんげんどもはこの時、やはりアメリカから持ち帰ったウシガエルを食用として養殖しようと計画していた。 しかし、偉い人ははたと気が付いた! 日本人は普通、不気味なウシガエルなど食わんと言う事に!! こうしてウシガエルの食用計画は日本人の食卓に定着せず、養殖場は壊滅。 逃げ出したアメリカザリガニはいつの間にか日本中に跳梁し、 北海道と東北北部に生息するニホンザリガニを差し置いて、 今ではザリガニと言えばアメリカザリガニを指すようになってしまったぞよ!  生命力が強く、一度に数百個の卵を産み無限に増殖するアメリカザリガニ。 無辜なる在来生物を貪り食い、豊かで清らな日本の水辺を荒らしまわるが為に、 遂に日本政府も重い腰を上げて2023年6月1日に本種は「条件付特定外来生物」に指定された! 今まで野放しだったこの邪悪な生物を討とうと、ようやく日本人も決意したぞよ! って事で、今まではその辺で誘拐してきて自由にペットにして遊ぶ事が出来たアメリカザリガニは、 ちょっと扱いが難しい動物となったぞよ。 一応拾って飼う事はOKとされているが、 移動させて別の水辺に離したり、無闇に誰かにあげたりすると犯罪になる。 販売、頒布、購入が出来なくなったと言うワケぞよ!  そんなアメリカザリガニを、本商品は鋏先から尾先まで、全長11センチサイズで立体化! 本種は多くの場合9センチ~最大でも15センチ程度なので、リアルな1/1サイズぞよね! 赤の濃淡が美しい彩色がまた豪華で、ご覧の通り尾節の先っちょまで色分けされている細かさ! これが300円とは・・・2019年ってまだまだ豊かな時代だったぞよねぇ・・・(溜息  触角なんかも実に細かく生物的なディテールが塗装表現されているぞよ。 ザリガニのフィギュアは生き物玩具ファンにも人気があるけど、 本商品は特に一目置かれている逸品とされる!  お腹側もこの通り見事な色分けぞよ! 造形もまずまず正確で、尻尾の腹肢もキモ可愛く再現されておりツボをついている。 お腹側だけ見るとメスっぽいけど・・・ハサミは立派だし、どっちなんでしょうね。  300円にしてギミック付きなのが「あそべる生物」の見所ぞよ! こちらのアメリカザリガニは、第1胸脚の鋏脚が付け根でスイング可能となっている。  このように開いたり閉じたり出来るが、これはまずおまけ的可動ポイントぞよね。  本商品に盛り込まれた最大のギミックは別にある! 動物フィギュアファンを唸らせた驚異の機能とは・・・!?  つるんっ!!  な、な、なんと・・・! 頭胸甲と尻尾の甲羅がパージでき、脱皮する事が出来るのだ・・・! 一皮むけて一回り小さくなっちゃいました!  甲殻類であるザリガニは脱皮をする生き物であるぞよ。 大体2週間に一度くらい脱皮して、次第に大きく成長してゆく。 そんなザリガニの殻はカルシウムとキチン質で出来ているぞよ。 脱皮が近づくと、ザリガニは殻からカルシウムの成分を回収し、胃石として胃に蓄える。 カルシウム成分の抜けた殻は柔らかくなり、脱皮が容易になるぞよ。 こうしてふにゃふにゃになった古い殻を脱ぎ捨てると、ザリガニはこの殻を食って残りの成分も体内に取り戻す。 そうしてお腹に蓄えたカルシウム成分を再び殻に送って硬くなるのだ。 脱皮はザリガニの身体の様々なダメージや累積物がリセットされるタイミングでもあるぞよ。 例えば、鋏や脚がうっかり取れてしまっても、何度か脱皮を繰り返す事で元通り再生する事がある。 しかし、脱皮する事で失われてしまう大事なものもある。 例えばザリガニは触角の根元の平衡胞に砂を入れて水中でのバランス取りに使うが、 脱皮する事でこの砂が零れ落ちて無くなってしまうのだ。 だから、ザリガニを飼う時は水槽にごく小さな砂を敷いておかないと、 ひょっとしたら脱皮のタイミングで歩きがヘタクソになってしまう可能性があるぞよ。  と言う事でこちらの脱皮ギミック、ザリガニの生態を汲んだ面白い仕掛けなんですね! ぱっと見で着脱可能に見えないから驚きぞよね! 脱皮後の姿も違和感ないし、実に良く出来たギミックぞよ!  ちなみにこのギミックの前身となるものとして、 食玩「昆虫の森 カブト ザリガニ クワガタ 水中からの挑戦(2013年4月)」というパッケージに収録された 「アメリカザリガニ」があげられる。 こちらはクリア成型色で殻の中には緑のザリガニが入っていると言う凝ったもので、 当時は一番人気で全国のジャスコでザリガニ狩りが行われたとも言われる逸品ぞよ! てっきりわたくしは本商品はこの原型を再利用したものと思ったが・・・ どうもよく見比べると別造形かつサイズも異なるようなので、本商品は食玩を元にしたリメイク的ポジションみたいぞよ。 「みずべのなかま」において、ザリガニは「あたらしいなかま編(2020年5月)」、 「ザリガニ・ヤドカリ・カメ(2020年12月)」、そして最新弾の「自然にあつまれ!(2025年3月)」で再録されており、 これまでに4つのカラバリが登場しているぞよ。  アメリカザリガニと言えば・・・我らがアニアシリーズでも発売されたばかりぞよね! 右は「アニア 大自然の最強いきものセット(2024年7月)」というパケに含まれたアメリカザリガニ。 これも逞しく立派な造形が実に格好良かったが・・・、  裏返してみるとなんとまさか! 300円ガチャの方が色数が多いと言うね・・・!! ただし可動ポイントはアニアの方が多く、決して過去のガチャに負けている訳ではないぞよ! ちなみにこのアニアザリガニ、6月に単品パケに昇格され、カマキリと一緒に「AL」ナンバーで通年販売が開始されるみたいぞよ。  続いて「アカミミガメ」ぞ! こちらも元はアメリカに生息した体長28センチ程の亀・ミシシッピアカミミガメの幼体で、 所謂「ミドリガメ」をモチーフとしたもの。 日本へは1980年代以降にペットとして大量に輸入された結果、 巨大化して飼いきれなくなったものが水辺に捨てられ定着・繁殖。 やはり在来動物の生育環境を奪ってしまい大問題となった。 その為、ミシシッピアカミミガメもザリガニ同様、2023年6月より条件付き特定外来生物に指定されているぞよ!  本商品の発売された2019年には、まだこれらの動物達は「みずべのなかま」として身近に親しまれていたが、 勿論在来生物を脅かす存在として広く知られてもいた。 それから数年たって今ではすっかりお尋ね者ぞよ。 一度野生に定着してしまったザリガニやミドリガメを、いくら法律で縛ったとて速やかに駆除すると言う事は難しいだろう。 奴らは増えすぎたぞよ・・・! しかし、おろかなにんげんどももこうして重い腰を上げた事だし、 これらの外来生物は今後緩やかに減っていき、遠い未来には根絶される事が予想される。 いつか玩具を見て、そう言えば昔はこんなのがその辺にうじゃうじゃいたなぁ、と思い返す日が来るのかもしれないぞよ・・・。  こちらのアカミミガメ、後の弾でも何度か再録されており、 過去に別バージョンもレビューで取り上げているのでここではサクッと見ていくが・・・ 再録されるたびに簡略化されてゆく彩色が、初出となる本商品では重塗装されており見所であるぞよ!  甲羅や手足にばっちり模様がプリントされているばかりか、 良く見ると各部モールドにスミ入れまでされているじゃないか~!  300円とは思えぬ豪華彩色! こだわりの逸品ですぞよ!  最近のガチャではデジタルプリントなども導入され、 バンダイの「いきもの大図鑑アドバンス カメ01 ミシシッピアカミミガメ(2024年8月)」では リアルな甲羅模様をデジタル再現していたが、 本商品は昔ながらの彩色で素朴な仕上がりぞ。  爪先やお腹側もちゃ~んと彩色されています。 豪華ぞよね!  「あそべる生物」としてのギミックは甲羅への収納変形。 ミシシッピアカミミガメのフィギュアでは定番のギミックだが、全身すっかり隠れるものはなかなかない。 収納変形では本商品が最も優れていると言っても過言ではない隠れっぷりぞ!  軸移動やスイングで上手い事収納しています。 まさにあそべる生物・・・!  この収納用の可動ギミックを利用してポージングを付ける事も可能。 簡易可動フィギュア的な面白味も備えるぞよ。  「あそべる生物フィギュアシリーズ みずべのなかま みんなの大自然(2023年3月)」バージョンのアカミミガメと並べて~。 ご覧の通り近年の再録ではすっかり色数が減ってしまったが、 白目が新たに彩色されているのは注目ポイント。  再録版では模様の形も簡略化されていますね。 アカミミガメは「みずべのなかまザリガニ・ヤドカリ・カメ(2020年12月)」、 「みずべのなかま みんなの大自然(2023年3月)」、 そして最新弾の「みずべのなかま 自然にあつまれ!(2025年3月)」に再録されており、 本商品と合わせて過去に4バージョン出ているぞよ。  ラストはこちら! 「ホンヤドカリ」ぞよ! なんとびっくり、滅茶苦茶彩色が綺麗ぞよね! これはリアル感出てますぞよ~。  こちらも過去に再録バージョンを紹介済み。 過去レビューでは種までわからないものの、右の鋏が大きいのでホンヤドカリ科の何かだろうと書いたが・・・、 本商品のラインナップにははっきり「ホンヤドカリ」と書かれてあるではないか~っ! なぜか「みずべのなかま みんなの大自然」バージョンだけ「ホンヤドカリ」表記でなく「ヤドカリ」表記でのラインナップだったのです。 謎ぞよ。  ホンヤドカリは日本の磯部では最も目にする機会の多いポピュラーなヤドカリぞよ。 緑っぽい体色に縞模様の触角と脚を持ち、ホンヤドカリ科の特徴として鋏脚は右側が大きく発達している。 砂浜ではなく、潮が引いた後のくぼみに残された潮だまりや石の下などに良く見られるぞよ。 体長は1センチ程でごく小さく、ペットとしても飼育しやすい身近な「みずべのなかま」である。  臆病な性質で危険を察知すると素早く殻に閉じこもって身を守るホンヤドカリ。 2~3センチくらいの小さな貝を背負っており、 生息域や成長段階にもよるが、イソニナやイシダタミ、 コシダカガンガラ、スガイなど、殻口が広く小型の貝を利用するぞよ。 本商品ではオレンジの綺麗な巻貝を背負っていて可愛い感じだ!  この巻貝も非常に丁寧な彩色で驚かされますよ~。 これが300円とはね・・・! ちなみに海へ遊びに行った帰りにその辺に落ちている綺麗な貝殻を拾っておみやげに持って帰ってきたおろかなにんげぇ~ん! ちゃんと中身確認したぞよか~? ひょっとしたら奥の方でヤドカリが干からびているかもしれないぞよよ~。  ヤドカリ本体もかなりの重塗装。 脚の縞々など良く出来ているが、触角に縞が無いのは流石に細かすぎたのだろう。 ホンヤドカリは鋏脚に小さなツブツブの棘が生えている事も特徴の一つだが、これも再現されていない。 しかしちょっと目の粗い彩色が施されており、雰囲気を出そうとしてるのが見て取れるぞよ。  本弾の彩色、全体的に筆ムラが生物的ディテールの演出に使われているのが面白いポイントぞよね! 手作り感溢れていてかえって豪華に感じますよ~。 今はこんなに丁寧な彩色、300円ガチャでは難しいだろう・・・! 当時にしてもかなり気合の入った作りだったのではないぞよかな?  物凄い情報量だ! この弾はハズレ無しぞよ!  お腹側もばっちり重塗装。 「あそべる生物」としてギミックも搭載されており・・・、  左右の鋏脚が付け根でロールし表情付けが可能となっている。  ちょこっとシルエットを変える事が出来るぞよ。 余談だが本商品は鋏脚が組み立て式となっていたが、 2023年の「みんなの大自然」では組み立て済みで封入されており、 ミニブックには「可動ポイント」と記されていたがギチギチで動く気配がなかった。 やっぱり間違って接着されていたのでは?と言う気もするぞよ。  そしてホンヤドカリのギミックはこれだけではない・・・! なんと本商品、巻貝の着脱が出来るのだ・・・! くるんと巻いたお腹もばっちり造形されており、ホンヤドカリの真の姿と生態を完全再現している! これは凄いぞよ~っ!  普段は隠れている腹部も緑の濃淡で美しく彩色されている。 都合上、巻貝と合体する時は中で擦れてしまうので塗装ハゲが心配だが・・・ 一応今回着脱してみた感じではぱっと見傷はつかなかったぞよ。 ヤドカリは巻貝と合体する為に腹部に腹肢を持っている。 卵から羽化したゾエア幼生が脱皮を繰り返し、メガロパとなるのだが、 メガロパ幼生期には左右で対になっている腹肢が成体になる頃には左側のみ残るのだ。 これは巻貝を支える為の進化と考えられる。 そして、抱卵の為に利用するメスでは特に発達し、オスは退化傾向にあるぞよ。 ホンヤドカリの場合はメスでは4本、オスでは3本あるみたいぞよ。 本商品ではギミックの都合でつるんとしているがご愛敬ぞ。  中身だけ出しても可愛いホンヤドカリ! 塗装ハゲが怖いのでこの重塗装バージョンは巻貝と別々に飾る事にするぞよ~。  このツブツブ感・・・いかにも生き物めいてキモカワである!  「みずべのなかま みんなの大自然(2023年3月)」バージョンと並べて~。 ご覧の通り後のバージョンでは生物感が薄れ、 明るめの彩色が施された絵本の中のキャラクター風味になってしまったぞよ。 こっちも可愛くて悪くない・・・! が、ホンヤドカリの特徴の縞模様などがオミットされている。 「みんなの大自然」バージョンで「ヤドカリ」表記だったのはその辺の都合もありそうだ。  巻貝の色も変わりました。 この原型は「みずべのなかま ザリガニ・ヤドカリ・カメ(2020年12月)」、 「みずべのなかま みんなの大自然(2023年3月)」、 そして最新弾の「みずべのなかま 自然にあつまれ!(2025年3月)」に再録されており、 都合4色のバリエーションが存在するぞよ。  みずべのなかまを集めよう! 同じ原型でも彩色違いでがらっと印象が変わるのが面白いぞよね! アニアと組み合わせて遊んでも良い感じだ!  「みずべのなかま」シリーズはここから始まった・・・! 過去の全原型が網羅された総集編弾のリリースに合わせて、元祖「みずべのなかま」の紹介でした。 重塗装にギミックも面白い傑作ガチャ! 物価がどんどん上昇する昨今では在りし日の思い出ぞよよよよ~っ!  腕が飛んでも脱皮で元に戻るとは、便利な生き物もいたものだ・・・! 時たま深刻なダメージも負うが基本的には能天気に展開されてゆく「虫屋ときつね」もよろしくぞ! :このリンクを踏んで何かポチるとわたくしにささやかな報酬が入りサイトの運営費となるのでよろしくぞ! ・「自由研究シリーズ No.24 EX-6 いきもの編 アメリカザリガニ(メタリックレッド)」 ・「アニアキングダム カワウソ村のどうぶつセット (ホワイトパールVer.)」 ▲TOP |
■海洋堂 カプセルQミュージアム イモムシストラップ コレクション イモコレ!Vol.5  海洋堂より、2023年8月発売の一回400円ガチャ。 2013年に開始したリアルなイモムシフィギュアシリーズ「イモコレ!」 前弾から約3年ぶりとなる第5弾ぞよ!  ラインナップは「ナミアゲハ」、「ツマグロヒョウモン」、「モンシロチョウ」、 そして「オオゴマダラ」の幼虫と蛹からなる全5種であるぞよ! 世界では16万種、この日本では6500種以上見られるという鱗翅目は、 この世で最も美しい昆虫の一つであるが、そのイモムシとなるとなかなかリアルな玩具は無いものぞ! 海洋堂の「イモコレ」は妥協無しの超リアル路線、かつこれをストラップにしちゃおうと言うのが面白いコンセプトなのだ!  造形総指揮は恐竜造形でも知られる松村しのぶ氏となっており、ファンにも注目の一品。 「とってもリアル、よく見ればキュートなイモムシ大集合!」とコピーがついているように、 今回リアルイモムシが次々に登場するので苦手なにんげんは要注意だ!!  じゃん! まず初めはこの日本で最もポピュラーに見られる蝶の一つ、「ナミアゲハ」の幼虫ぞよ! 蝶や蛾からなる鱗翅目は、卵から矮小な幼虫の状態で生れてきて、 それが蛹を経て成虫の蝶へ変態する完全変態昆虫であるぞよ。 鱗翅目の幼虫は芋虫や毛虫などと呼ばれる形態をして、盛んに栄養を取って体を成長させる事のみを目的に生きているのだ。 幼虫も成虫と同じく、体は頭部、胸部、腹部の構造からなる。 頭部は割に硬く、胸脚のついた胸部、そして腹脚のついた腹部はぷにぷにとしているぞよ。 一般的な蝶の場合、胸脚は成虫と同じく3対、 補助となる腹脚は4対と、末端に1対ついている事が多いぞよ。 このナミアゲハの幼虫を見ると・・・胸に3、腹に4、末端に1で基本形ぞよね! 幼虫はぷにぷにの体を伸び縮みさせながら、この小さな足を使ってむにむにと歩くわけです。  鱗翅目の幼虫は食べるのもが概ね決まっているぞよ。 ナミアゲハの幼虫はミカン科の植物を寄主として繁栄してきた生き物で、 成虫はフセツの化学感覚子で葉の化合物をかぎ分ける能力を持ち、 幼虫の餌に適した植物に卵を産む工夫をする。 もし好みでない葉に卵を産もうものなら、その子は決してご飯を食べずに餓死してしまうからだ。 なぜ蝶が偏食かと言えば、こうして寄主植物を選ぶ事で他の種と生息域を棲み分けているからであるぞよ。 つまり、蝶は植物と共に繁栄する生き物なのだ。 ナミアゲハが日本で広く見られる理由もここにある。 そう、おろかなにんげんどもが食料に適したミカン科の植物をあちこちに持ち込み、 育てるようになったから、蝶も共に生息域を広げ繁栄出来たのだ。 ナミアゲハはおろかなにんげんどもと共に生息域を広げてきた動物の一つなのである。  鱗翅目の幼虫は卵から産まれてくると、寄主となる植物をむしゃむしゃ食いまくる、 栄養が体に貯まってくると、それまで着ていた小さな皮を脱ぎ捨てて一回り大きな体になる。 これを脱皮と言うぞよ。 孵化したての幼虫は1齢幼虫、脱皮すると2齢、3齢と齢を重ねてゆき、姿も大きくなってゆく。 そうして育ち切ったイモムシの中のイモムシを終齢幼虫と呼ぶぞよ。 エネルギーを蓄え終えた終齢幼虫はやがて蛹の姿になるのだ。 この脱皮の回数は種類によって異なり、 ナミアゲハの場合は黒っぽい矮小なイモムシとして生まれてきて、4回脱皮して蛹になるので、 5齢で終齢幼虫ぞよ。 本商品はそんな立派な緑の終齢幼虫の姿が再現されていると言って良いだろう。  続いて「ツマグロヒョウモン」の幼虫ぞよ! 元々は熱帯・温帯域に広く分布した蝶で、日本ではその昔、近畿地方以西でしか見られなかった種であるが、 近頃は気候が温暖になってきた影響で関東でも普通に見られる種となりつつある。 成虫はその名の通り、オレンジにヒョウ柄の入った翅を持ち、メスでは翅の端が黒く色づき、白い帯が美しい。 そんなツマグロヒョウモンの幼虫は・・・なんとびっくり! トゲトゲの生えた勇ましい姿をするばかりか、毒々しい色も目立つ恐ろしい姿をするぞよ・・・! これは明らかに毒ありますよと周囲に警告を発しているぞよね・・・!? しかしご安心、この見た目ははったりであるぞよ。  実はツマグロヒョウモンの色と見た目は敵を脅かす為の見せかけに過ぎんのだ。 トゲトゲはぷにぷにとして全く武器として役に立たないし、勿論毒も持たない。 手で触っても別に何の事は無いイモムシであるぞよ。 そんなツマグロヒョウモンが寄主に選んだのはスミレ科の植物であるぞよ。 これはパンジーやビオラなど、お母さんがお庭に植える植物が含まれている。 つまり、身近な植物に付き食害を与える害虫であるぞよ。 従って、毒々しい見た目も相まっておろかなにんげんどもには嫌われ、退治されてしまう事もしばしば。 近頃は分布を広げて、数多跳梁するから尚更ぞよ!!  ツマグロヒョウモンも5齢で終齢幼虫となる。 実際にはこのトゲトゲの先に細かな毛が無数に生えているのだが、フィギュアでは再現できないのでややデフォルメされているぞよ。 しかしぱっと見には本物と見紛う毛虫感だ・・・! 脚の数も蝶共通の基本形で正確ですね。  続いてこちらもポピュラーな所謂青虫、「モンシロチョウ」ぞよ! 成虫はほんの小さな白い蝶で、アゲハと共に身近によく見られる可愛いヤツぞよね! これもおろかなにんげんどもの生活と密接に関わる昆虫であり、それはアブラナ科を食草とする点にある。 即ちキャベツや白菜、大根など多くの野菜を食って育つ生き物なのだ! これも人間が畑を耕し、野菜を育てるようになって一緒に分布を広げてきた隣人と言えるだろう。 それだけに、農家ではとても嫌われていて、見つけ次第抹殺される運命にあるのだが、そこはしぶとい生命の神秘。 この令和の世にも絶やす事は出来ず、その辺を気ままに飛んでは野菜に卵を産んでいるから逞しいのだ。  この日本へは縄文から弥生時代に持ち込まれ、 奈良時代より盛んに栽培されるようになった大根と共に引っ越してきたと考えられているぞよ。 モンシロチョウの幼虫が緑色をするのも寄主植物と関わりがあり、 つまり野菜にくっついて同化し、外敵に見つからないようにするための知恵なのだ。 昆虫も色々考えるものである。  そんなモンシロチョウの幼虫は孵化したては矮小な毛虫の如き姿をするぞよ。 生まれたてには自分の入っていた卵の殻を食べ、含まれた豊富な蛋白質を最初の栄養とする事で知られている。 通常4回脱皮をして終齢幼虫となるので、このフィギュアはやはり5齢の姿であると考えられるぞよ。  3種のイモムシを比べてみよう! みんな一見するとシルエットが異なるが、体の部位や脚の数など蝶の基本形で共通であるぞよ。  イモムシの基本形としては頭部に6対の小さな個眼を持つ事があげられるぞよ。 このフィギュアの場合、ナミアゲハとモンシロチョウでは判りやすい。 顔の左右にぽちぽちある黒い点が目なのである。 しかし数えてみると・・・おっと、どちらも5つしかないぞよ。 大体の場合、イモムシの目は一列目は発達しているけど二列目の端っこはほんの小さくて目立たないんですね。 と言う事であんまり小さいので省略されているのだろう。 成虫となった蝶は複眼を備え、とても目が良い事で知られているが、 幼虫時代は6つの個眼で物を視ているとは面白い違いぞよね! 成虫との違いと言えば、口の形も違うぞよ。 成虫ではストロー状の口器で花の蜜を吸う蝶であるが、幼虫の頃は顎状の口で葉を食うのに適した形をする。 この葉を食うむしゃむしゃした動きがよく見ると愛らしいのである。  そして本商品・・・どれもお尻にストラップ紐がついている・・・!! お、おい~・・・海洋堂! こんなストラップ持ち歩いてたら街中で悲鳴が上がっちゃうぞよ!!  わたくしが思うに、どうしてイモムシが嫌われるかと言うと、 まずイモムシ自体が外敵に警告を発する奇抜な色を纏い嫌われるような努力をしている事も上げられるが・・・ 体がぷにぷにとして不安定な事が大きいと思うぞよ。 こんなのちょっと触っただけでプチっと破れて中身が飛び出しちゃいそうで怖いぞよね!? それで言うと本商品はカチコチのPVC製なので、弄繰り回しても全然平気なのである。 イモムシ嫌いな人も安心して遊べるのです。 このフィギュアを一つ持てば、おろかなにんげんどももイモムシ嫌いを克服できるかもしれないぞよ! ちなみにこのシリーズ、初期は柔らかくぐねぐね曲げられるベンタブル仕様でほんの300円だったぞよ。 際限無い物価高が憎いぞよーっ!!  続いて「オオゴマダラ」の幼虫はラインナップ中唯一要組み立てであるぞよ。 一応がっちり組み付くようになってるけど、 上半身行方不明にならないようにストラップとして使用する人は接着した方が良いかもしれませんね。  合体して完成! 「オオゴマダラ」の幼虫ぞよ! 体の作りは他の幼虫と一緒だが・・・ こいつも明らかに毒っぽい色形をしているぞよーっ!!  東南アジアに広く分布し、日本では沖縄諸島や先島諸島で見られるオオゴマダラ。 成虫は前翅長7センチ以上にもなる国内では最大級の蝶であり、 白地に黒いまだら模様の翅をふわふわさせながら優雅に飛ぶ様が美しい。 マダラチョウ類共通の特徴として、成虫のオスは腹部末端にブラシ状のヘアペンシルと言う器官を持ち、 ここからメスを惹き付けるフェロモンを分泌し、番の相手を探すと言うものがあるぞよ。 このフェロモンは香水など、おろかなにんげんどもが身につける香り成分・パラベンを含む。 それが為に、香水をぷんぷんさせているにんげんの周りに集まってきたりもするぞよ。  そんなオオゴマダラの幼虫も5齢で終齢幼虫となるぞよ。 食草はキョウチクトウ科のホウライカガミに限られグルメである。 長いつるが伸び、海岸近くに多く見られる植物で、アルカロイドを含み有毒である為、 普通この草は食えんのだが、オオゴマダラの幼虫は毒の影響を全く受けないばかりか、 体内に溜め込んで利用するしたたかさを持っているぞよ。 つまり、葉由来の毒を帯びる事で、捕食者から身を守っているのである。 これは成虫になっても消える事がなく、 鳥などの捕食者はうっかりオオゴマダラを食うとあんまり不味くて吐き出してしまう程だという。 角を生やし、見るからにヤバ気な模様のついた幼虫の毒々しい見た目は、 まさに己に毒がある事を警告する為の警戒色なのだ! ちなみにぷにぷにの角は刺さないので触っても平気ぞよ。  そして最後のラインナップは、そんなオオゴマダラの蛹になった姿・・・、 「オオゴマダラの金色の蛹」ぞよ!  20日くらいかけて葉をもりもり食べ、エネルギーと毒を体内に溜め込んだ幼虫は蛹の姿になるぞよ。 そこから2週間~1か月くらいかけて体をドロドロに分解し、蛹の中で成虫の姿へと再構築するのだ。 幼虫の体内には成虫の体の元となる成虫原基と言うものが予め用意されており、 これを元に成虫の姿が形作られてゆくぞよ。 イモムシと蝶では生活様式がすっかり変わってしまい、最早別の生き物のようである。 しかし、幼虫の頃に覚えた嫌な思い出を成虫になっても蝶は覚えていて、 類似のシーンで回避行動を取ったりする事から、成虫になっても幼虫時代の事はほんのりと覚えているようである。 ま~、あえて忘れる理由も無いので当然と言えば当然ですが・・・ 神経系と共に、記憶もばっちり引き継がれているのだ!!  さて、オオゴマダラの蛹と言えば金ピカな事で良く知られている。 わたくしの幼少期に持っていた図鑑などにも、この金色の蛹は生命の不思議として特集されていた記憶があるぞよ。 まるで金属めいて黄金に輝く蛹は勿論、金属で出来ているのではない。 表面のクチクラ質と内部の層状構造による多層膜干渉が金属めいた光を発する、要は構造色であるぞよ。 蛹になりたてのオオゴマダラはまだ黄色い色をしているが、時間が経つにつれて次第に光沢を帯び、 2日ほどですっかり黄金色になる。 しかし羽化が近づくにつれてまた光の反射が鈍くなってゆき、 蝶が殻を脱ぎ捨てる頃には翅の模様が外からも見えるようになって、すっかり輝きが失せてしまっているぞよ。 なんでもこの黄金の輝きは幼虫の頃に食った葉に含まれるカロチノイドの影響で、 青色の光が吸収され反射されず、結果的に金色に輝くのではないかと考えられている。 何れにしても、このような黄金の輝きは生命の神秘であって、中の蝶が完成するか、あるいは死ぬかしても失われてしまうぞよ。 あんまり美しいからと言って摘み取って宝物にしようとしても、輝きは保存できないというワケだ。  本商品ではそんな黄金の輝きを、クリア成型色にメタリック塗装を施す事で再現している。 斑紋もただ黒をプリントするのでなく、外周を黄色で色分けする事でリアルさを表現しているのだ。 こりゃあ面白い仕様ぞよね! オオゴマダラの蛹がどうしてこんな風に輝くのかと言うと、実際のところ良く判らん。 毒のある事を鳥などの外敵に警告しているのかもしれないし、 周囲の光を反射して景色に溶け込んでいるのかもしれないし・・・ こんなにピカピカではかえって目立ち悪戯されそうだが、今日までしぶとく生き残っているという事は有効なのだろう。  毒々しい見た目の幼虫が黄金の蛹になり、成虫では真っ白に羽化するとは全く不思議な蝶であるぞよ! フィギュアでも集めて並べたくなっちゃうぞよね!!  オオゴマダラは大人しく、またでっかい事も影響しているのか頑丈で長生きな為に、 全国の蝶温室で飼育されているぞよ。 蝶を飼う事は食草となる寄主植物を飼う事と同義である。 幼虫は蛹になるまでの20日間でホウライカガミの葉を30枚くらい食べるというから、 飢えないように準備してやる必要があるぞよ。 羽化した成虫は走行性を殆ど示さずひらひら気ままに飛んでいるだけで大人しく、 体も丈夫で4か月くらい長生きする事もあり、環境さえ準備できれば比較的飼いやすいとされる。  例えば東京は元渕江公園内にある「足立区生物園」には蝶の大温室があって、 もちろんオオゴマダラも飼育展示されている。 そしてなんとおみやげにはオオゴマダラやアサギマダラなどの蛹の抜け殻を瓶詰にして売っているのである。 しかもこの抜け殻シリーズ、通販で気軽に買う事も出来ると言うのは驚きぞよ・・・! 竹ノ塚なんてその気になればぴゅっと行って帰ってこれる距離である。 わたくしも是非ともこの足立区生物園の昆虫館には行って見たいと思っているが・・・ そこは出不精ひきこもりわたくし、思うだけでまだ足を運んだことがないのはつくづく情けない事です・・・。 そのうち行くぞよ!! ・・・たぶん・・・。  そしたらおみやげに蝶の蛹も買ってみたいと思うのだが・・・、 生物由来の標本だからその辺に置いといたら虫に食われそうで怖いぞよ。 わたくしの部屋や倉庫には玩具の詰まったケースが無限に置いてあって、 このうえ実物標本の管理などとてもできんのだ。 瓶詰で封印されていたらカツオブシムシの入る隙間もないとは思うが・・・どうなんですかね?  鱗翅目とはおろかなにんげんどもが最も愛し、また身近な昆虫であるが、 その造形難易度の高さから成虫のリアルな再現玩具の類はなかなか見られない。 2024年にはバンダイの「いきもの大図鑑」からアゲハが発売されて、 今のところ翅脈が3D再現されたこれが最もリアルであるぞよ。  いきもの大図鑑のアゲハは本物よりちょっと大きいけどご愛敬。 あと、こいつはナミアゲハじゃなくてキアゲハだ。 本商品、イモコレのナミアゲハは約6センチ、ツマグロヒョウモンは約6.5センチ、 モンシロチョウは上体を起こした姿で約5.5cmなので6センチくらい、 オオゴマダラ幼虫は約7センチ、蛹は約4センチで造形されている。 ナミアゲハとオオゴマダラはまずまずリアルなサイズ感、ツマグロヒョウモンはやや大きめで、 モンシロチョウは明らかに拡大サイズぞよね。  オオゴマダラは幼虫も大きいのでいきもの大図鑑のお花台座に乗せてもこの存在感・・・! しかし、悲しいかな鱗翅目の幼虫は食うものが決まっている。 こんなお花に乗せた所で、オオゴマダラ幼虫は餓死する定めであるぞよよよよ・・・。  産まれてきてはもりもりと葉を食うだけの健気な生き様、 鱗翅目の幼虫とは実に愛らしい生き物であるが、 にょきにょきぷりぷりの姿でおろかなにんげんどもには不気味がられている。 一方でやはり、何か人の心を擽る愛嬌があるのも事実で、 イモムシをモチーフとした可愛いキャラクターは様々いるぞよ。 ねんどアニメ「ニャッキ!」に登場するこのニャッキなどはまさにその代表格であろう。  しかしニャッキには毒々しい模様も、わきわき動く足もなくデフォルメされている。 どうやらおろかなにんげんどもを怖がらせる要素はこの無数に生えた足にも秘密があるみたいぞよね。  蛹の玩具となるともっと珍しい!! 本商品はストラップ仕様だが、まさにオオゴマダラの蛹はこのようにお尻で葉っぱや樹にぶら下がっているぞよ。 このように頭を逆さまにぶら下がるものを垂蛹型と言う。 羽化する時も当然、ぶら下がったまま頭を下に現れるのだ。  せっかく可愛いストラップなのだから、カメラ鞄にでも付けたい気分だが・・・、 あんまりリアルなのでちょっと勿体ないぞよ。 ガチャでダブった人は是非普段使いしましょう。  リアルな幼虫玩具と言えばこれ一択・・・! 海洋堂の放つ長寿シリーズ「イモコレ」第五弾でした! 2024年の科博特別展「昆虫MANIAC」でイモムシ標本箱を見物してから、 わたくしも是非鱗翅目幼虫の玩具が欲しくてたまらなくなったが、 リアルなものがなかなか売っていないんですね! ほんと幼虫を特集したシリーズはこのイモコレくらいなもの。 こりゃあ幼虫ファン希望の星ですぞよ。 おろかなにんげんどもも、ガチャ売り場で見つけたら即ゲットぞ!! ダブってもストラップとして使えるからお得だぞ!!  通勤通学のお供に、「ばらむツZ」9巻で昆虫展レポを読もう・・・! :このリンクを踏んで玩具や日用品をなんでも買うとわたくしにささやかな報酬が入りサイトの運営費となるのでよろしくぞ! ・「はらぺこあおむし+ぬいぐるみ ギフトセット」 「サン・アロー はらぺこあおむしカラフルグリーンぬいぐるみ」 イモムシをモチーフとした有名作品と言えば、エリック・カール作の絵本「はらぺこあおむし」もある。 しかしここまでで鱗翅目幼虫の体の構造を学んだおろかなにんげんどももお気づきの様に、 このはらぺこあおむし、胸脚が2対、腹脚が1対しかないぞよ。 鱗翅目の中でも、シャクガの幼虫は胸脚は3対、腹脚は末端の1対しかないものもいる。 幼虫の胸脚は成虫の脚に相当する部位なので、昆虫の特徴として6本あるのが自然であるが・・・ ま、そこははらぺこあおむしの特徴にして不思議であるぞよ。 ひょっとしたらエリック・カールは昆虫の脚=6本と考えて、幼虫の脚も全部で6本として描いたのかもしれないぞよね。  その後100均ケースにしまって標本箱風に飾っているぞよ。 なかなか可愛いでしょ~。 ▲TOP |
■タカラトミーアーツ あそべる生物フィギュアシリーズ モンスターフィッシュ 日本の海の怪物たち  タカラトミーアーツより、2024年12月発売の一回300円ガチャ! 2024年ラストあそべる生物フィギュアぞよ・・・ッ!!  2021年に「世界釣大戦 モンスターフィッシュ」として始まり、 2022年には「世界釣大戦モンスターフィッシュ ~Different colors~」が登場、 2023年には「世界釣大戦 モンスターフィッシュ なぞの怪魚をおえ!」と続いた「モンスターフィッシュ」シリーズ。 2024年弾となる今回は「日本の海の怪物たち」と題し、日本の海で見られるユニークな生物をチョイス。 ラインナップは「オオカミウオ」と「タカアシガニ」がそれぞれAカラー、Bカラー2色ずつの計4種となっているぞよ。 どちらも水族館で普通に見られるお馴染みの生き物ぞよね! 公式スペックでは本体サイズ12.5~14.5センチとなっており、いつも通り300円にしてめちゃデカいのがウリである。  それでは中身を見ていこう! こちらは黒い「オオカミウオA」ぞよ! 見た感じ黒一色っぽいがよく見ると濃淡がついており丁寧仕上げである。 今回初登場の新規造形ラインナップで、本弾の目玉であるぞよ!  トップ。 オオカミウオは茨城県から北海道の水深50~100メートルの岩礁域に生息する全長1メートル程の魚であるぞよ。 その名の通り、巨大な歯と厳つく狂暴な顔つきが特徴的な為に、狼の名を冠される事となったが、 見た目に反して極めて臆病な性格をしており大人しい。 それが為に飼育も容易と言われ、 日本中の水族館で見られるからおろかなにんげんどもも親しみがあるのではないだろうか? ・・・ちなみに飼育が容易と言うのはルートがあれば手に入りやすく狂暴性が低いと言う意味であって、 もしオオカミウオをおうちで飼おうとしたら全長1メートル級をゆったり飼える巨大水槽に、 冷水の海域を再現し、水温を低く保つための工夫や、 生餌しか食わんのでホタテとか毎日買わなきゃいけないしで、とてもではないが面倒見切れんぞよ! どうもオオカミウオをペットにするのは難しそうだ。  オオカミウオはスズキ目ゲンゲ亜目に属するオオカミウオ科の海水魚。 全体に鱗は持たず、ごく小さな円鱗があるばかりの皮膚は極めて分厚く強固で、ぬめりを持つぞよ。 浮袋を持たないので岩場でもたっとしている事が多く、 水族館でも恥ずかしがり屋なのかガラスから目を背けて底に転がっている姿がよく見られる。  続いてこちらは「オオカミウオB」カラーぞよ! 真っ赤なボディにグラデ彩色が施され一見するとこちらの方が豪華に見えるぞよね! また、白目が彩色されているのも注目ポイント。 オオカミウオは黒~黒褐色が普通のイメージでこれはやや赤みが強すぎる気もするが、 どうもこんな風に鮮やかに発色する個体もいるようだ(写真写りの問題かもしれんが)  トップ。 造形はAと同じカラバリ仕様ぞよ! 体表にぬめりを持ち、これが臭みの原因となる為捕まえたあとはすぐに絞める事が望ましいとされるが・・・ 適切な処理を行ったオオカミウオは脂がのった白身が大変に美味で、 近頃は通な食用としても注目されていると言うぞよ。 もっとも、流通や処理に手間がかかる事がネックで広く食卓に出回るまでには至っていないと言う。 こんなでっかくて恐ろしい魚が晩御飯に出てきたらびっくりしちゃうぞよね!!  オオカミウオは冬になると産卵すると言うが、 夏の終わりや秋ごろには既に卵を持ったものが釣り上げられる事もあり、よくわからんぞよ。 産卵期になると比較的浅い所までやってきて、岩の隙間に卵を産み、 オスが卵に巻き付くように抱卵し、春までは餌も食わずに外敵から守り続けると言うのは健気である。 繁殖期のオオカミウオはオスでは体が青みがかり、メスでは黄色く色づくと言うから、 どうも赤っぽい色はまだ幼い状態なのかもしれないぞよね。  オオカミウオ最大の特徴の一つは、この大きく発達した歯だろう! 鋭く大きな歯で好物のホタテやケガニ、ウニなどをバリバリと砕いて食うとは全くグルメな奴ぞ! これが為に、オオカミウオを捌くと胃から殻の破片が沢山出てくると言うのは、具合が悪くなったりしないのだろうか? また、ゲンゲ亜目に共通する形質として、背鰭が柔軟な棘条のみで構成され、軟条が退化している事も特徴とされる。  そしてオオカミウオはこのぎょろぎょろの目玉がコリ、コリ、と動いて周囲を見る事も知られているぞよ。 臆病で岩場に転がったり、隙間に隠れ住んでいる事の多いオオカミウオであるから、 じっと動かず視線だけ動かして危険を察知する為に目が発達したのだろう。  オオカミウオの存在は古くから知られ、特に北海道の凍てつく冬を越す為には、食用として重宝された。 アイヌの人々はこれを「チップカムイ(神の魚)」と呼んで大事にしていたぞよ。 これはオオカミウオを指して呼ぶ言葉ではなく、腹の膨れる鮭など大きな魚を神と呼んだようだ。 神様なので、飢えを満たす必要のない時には酒を含ませてリリースしたと言うのは面白いぞよね!  オオカミウオおしり。 魚に酒を飲ませる文化はしばしば見られ、 富山県砺波市の伝統行事ではコイに清酒を飲ませて放流し、厄払いを託すと言うものがあるぞよ。 インターネットでこの様子が話題になると、「動物虐待!」として批判の声が上がった事もあると言うが・・・ 全くおろかなにんげんどもは動物の気持ちを勝手に想像して自分の憂さ晴らしに利用してばかりいるものだ。 インターネットと言えば、このオオカミウオもインターネットのおろかなにんげんどもに利用された事がある。 なんでも福島近海で見つかる、原発事故の影響で怪獣化した怪魚として、 フェイクニュースとしてオオカミウオの姿が海外で取り上げられ、出回った事があると言うのだ! 前述の通り、オオカミウオは古くから存在が知られる普通の魚であるぞよ。 日本人はオオカミウオなんかいつでも水族館で見物出来るのに、 胡乱な外人はその存在すら知らんとは無知とはおろかにも哀れなことである。 やれやれぞ!  あそべる生物フィギュアは300円ガチャにして各部可動のアクションフィギュアである! オオカミウオも体が二か所でスイングし、くねくねした動きをつける事が可能だ!  そして首がボールジョイントなので上下左右に表情付けが可能ともなっているぞよ。  これがまたうにうにと動いて愛らしい。 勿論特徴的な歯の揃った口は開閉可能となっている。  同原型の赤バージョンも可動域は同様ぞよ。  水族館でもお馴染みのオオカミウオがアクションフィギュアに・・・! 未だかつてオオカミウオがこんなに遊べる仕様で玩具になった事があったろうか・・・ いや、ない!!  抱える程もある巨大魚なので、 このフィギュアも一般的なサイズの可動フィギュアやプラモなんかに持たせてみると雰囲気が出て面白いかもしれませんね。  お口の中も見せておこう! 鋭い牙は勿論、硬い殻を磨り潰す為の口内の歯もリアルに再現されている。 こりゃあ良く出来たオオカミウオ立体物ぞよ!!  続いて同時ラインナップのこちらは「タカアシガニA」カラーぞよ! 2023年9月発売のあそべる生物フィギュア「深海のひみつ 海・底・世・界」からタイトルを跨いでの再録となっている。 こういうパターンもあるんですね~。  脚が長い分こちらも大ボリュームのフィギュアぞよ! 鋏脚が可動ポイントで、その他の脚は二本ずつ成型されており組み付ける仕様だが、 ぽろっと落ちがちなので木工ボンドなんかで軽く接着してやると遊びやすくなる。 無論、ガチガチに接着するなら瞬間接着剤なワケですが、 分解できなくなるとそれはそれで困るのでわたくしは木工ボンド派なのだ。  前述の通り過去弾からの再録ですが、例に漏れず彩色が一部簡略化されているぞよ。 元々は前節にもまだら模様がプリントされていたのだが、 本弾では脚は長節のみのプリントとなり、白い部分が増えているのだ。 この模様はタカアシガニの特徴の一つでもあるので、ややダウングレードと言えるだろう。  しかもこっちのAカラー、真っ赤である! これではゆでガニと言ったところだろう・・・! タカアシガニは身の水分量が多く、水揚げしてしばらくするとドロドロに溶けて液状化してしまう為に食用には向かないとされている。 しかし港町では珍味として食されており、 なんでも料理の際には断面に大根を詰めるとだし汁が濃縮されたまま残り、美味になると言うぞよ。 もっとも、こういう工夫を知っていてもタカアシガニを茹でる程の巨大な鍋がなかなかご家庭にはあるまい。  続いてこちらが「タカアシガニB」カラー。 オレンジでスタンダードな色と言った趣。 やはり彩色は2023年バージョンより簡略化されているが、 造形のボリューム感と説得力があるので実物は意外と気にならんぞよ。  クモガニ科の蟹・タカアシガニは日本の深海に生息する世界最大級の節足動物であるぞよ! 系統的には古くに枝分かれした存在で、なんでも1200万年前には祖先的な種が現れており、 そこからタカアシガニの姿に進化して後、殆ど姿を変えないまま現代まで生きている、 所謂「生きた化石」と呼ばれる動物の一つであると言われている。 現生では1属1種のみ知られるが、化石種が4種見つかっており、そのうち2種は日本国内から報告されたものだと言うから、 古代からこの日本に棲む立派な日本の生物なのだ! もっとも、かつては日本固有種と言われていたが、1989年に台湾でも発見されている。  なんと言っても非常に細長い脚が特徴で、成体のオスでは特に鋏脚が発達し、 広げると3.8メートルにも達すると言うのはまるで海の怪獣ぞよね! 従って本商品はそんなタカアシガニの立派なオスを再現したものと考えられるぞよ。 甲羅も大きく、最大で40センチ級になると言うのはいかにも食えそうだが、 水深200メートルもの深さに暮らす深海生物の常として、 前述の通り水分量が多く美味しく食うのは難しいとは悩ましいトコロ。 ちなみに若年個体では甲羅に毛や棘が生えているが、成熟するにつれて抜け落ちてつるつるしてくると言うぞよ。  この長い脚を何に使うかと言うと、やはり餌を採る時に用いるのだ。 タカアシガニは動物食傾向の強い雑食性で、鋏で貝などを砕いてはひょいっと摘んで食うと言う。 深海は生命に乏しく、エサにありつける機会も稀な為に、あまり動かず手を伸ばして餌を探せるように進化したのだろう。 陸上でブラキオサウルスやキリンは首を伸ばしたが、タカアシガニは脚を伸ばしたという事ぞよかな? もっとも、愚鈍そうに見えて水中ではなかなかすばしっこく動くと言うぞよ。  世界最大の節足動物にして深海性の蟹と言うとさぞ希少な珍生物なのだろうと思いきや、 日本の水族館では比較的普通に見物できる巨大蟹であるぞよ。 特に蒲郡市竹島水族館は日本最大級の深海生物展示で知られ、タカアシガニを触れるプールまであると言う! なんでも全国の水族館で見られるタカアシガニは この竹島水族館に捕獲されたものを融通してもらっている個体が多いという事です。  それがあそべる生物フィギュアなら300円で手のひら大に楽しめちゃうのだ・・・っ!! わたくしは前回入手しそびれていたので嬉しい再録であった。  こちらも動くぞ、タカアシガニ!! 鋏脚が基部と腕節でスイングし、表情付けが可能です。  この長い腕で獲物を掴んで食うワケぞよ! 結構大きくシルエットが変わるので楽しいギミックだ。  ゆでガニバージョンもわきわき動くぞ! つぶらなおめめが可愛いね。  何か小サイズフィギュアの敵モンスターとして並べて遊ぶのも楽しそうだ。  戦え、タカアシガニ! 勿論野生下では鋏を用いて縄張り争いの喧嘩をする! カニノケンカぞよ!!  オオカミウオの場合は当然、縄張り争いの時には口を大きく開けて相手を威嚇する。 生き物はみんな、最も発達した部位を武器に用いて自分の力強さを示すのである。  節足動物の多くは交尾の時期になると、予めオスがメスを確保する「交尾前ガード」と言う行動をする。 タカアシガニの場合はこのようにオスがメスに覆いかぶさり、長い脚で捕まえてしまうのだ。 ま~このフィギュアはどっちもオスっぽいですが・・・。 BLガニぞよ。  珍しい深海生物の玩具も色々と集まってきたぞよな~。 ここ数年、わたくしの中で生物フィギュア熱が高まっており、 書いたレビューは2023年は140個以上、この2024年は120個以上、 一つのレビューで本記事のように複数種扱う事もあるので、紹介した動物は数えきれないほどだ。 とりわけこの2024年はだんだんと記事の内容もボリュームを増しているから、 全く我ながら素晴らしい活動である。 本サイトをタダで暇つぶしに利用しているおろかなにんげんどもも、 このようなわたくしに敬意を表して、 時たまはリンクからお買い物をし、貢献して頂きたい。 リンクの商品を買わずとも、リンクを踏んで日用品を買うだけでもわたくしの糧となるのだから頼むぞよ。  みんなで蟹を食おう!! タカアシガニはばらしてアニアの餌に使うのも良いかもしれないぞよ。  今回初登場のオオカミウオさん。 見ての通りでっかいんです。  と言うかわたくしはせいぜいデンキウナギ級だと勘違いしていたのだが、 普通に最大サイズクラスの造形だったのは嬉しい驚き。 メガロドンに匹敵ぞよ!  タカアシガニもモンスター級だ! 本家アニアと組み合わせて遊ぼう!!  オオカミウオもタカアシガニも、どちらも水族館でお馴染みの生き物である。 わたくしもついこの間、10月末にしながわ水族館に行ってこの2種を見物したばかりぞよ。 しな水は近くリニューアルの為に旧館は取り壊されると言うから、 おろかなにんげんどもも最後に足を運んでみたら如何でしょうか。 と言う事でしな水で見られる生き物を玩具で集めてみたぞよ!! オオカミウオとタカアシガニが加わって再現度アップだ!!  2024年ラストあそべる生物が日本の生き物とはめでたい感じだ!! オオカミウオ&タカアシガニをゲットして、共にお正月を迎えようではないか!! おすすめ弾ぞ!!  おまけ。 わたくしのお部屋には何百匹もの動物からポケモンまで数多展示されており数えきれない程ぞよ。 いよいよガラスケースもいっぱいになってきたのでスペースを節約しようと展示台を作ったりしている。 これは100均のフォトフレームを分解し、針金を通しただけのお魚ベースだ。 縦に並べられるのでちょこっと片付きました。 おろかなにんげんどももマネして良いぞよよ!  最強怪獣デストロイアが出現した事でも知られる「しな水」・・・ かの聖地もいよいよリニューアルされてしまうと言う・・・・! おろかなにんげんどもよ、足を運ぶなら今しかないぞよっ!! 「ばらむツZ」10巻のレポ漫画を読んで予習してから出かけるのだ!! :このリンクを踏んで何かポチるとわたくしにささやかな報酬が入りサイトの運営費となるのでよろしくぞ! ・「カニノケンカ -Fight Crab-」 ・「POP UP PARADE ゴールデンカムイ 杉元佐一」 ▲TOP |
■タカラトミーアーツ あそべる生物フィギュアシリーズ いきものフシギ大列伝  タカラトミーアーツより、2024年11月発売の一回300円ガチャ! 地球上に存在するちょっとかわった生態の動物達をフィーチャーし、 一般的な認知度は高い一方で、立体化の乏しかった生物をセレクトする弾となっている。 過去弾だと「奇妙ないきもの博物誌」に近い雰囲気ぞよね。  「あそべる生物」はこのご時世に一回300円とは破格であるが、 カプセルも色分けされており見分けやすくユーザーフレンドリーであるぞよ。 全メーカー、見習うべし!  ラインナップは「モグラ」、「ホシバナモグラ」、「ブロブフィッシュ」、「チンパンジー」の全4種。 サイズは約7~11.8cmが公式スペックぞ。  それでは中身を見ていこう!! まずはこちら・・・「モグラ」ぞよ!! おーっ! 正に知ってはいるけどリアルな玩具を見た事がない動物ではないかーっ!  モグラは真無盲腸目の哺乳類であるぞよ。 北方真獣類の中でも翼手目、食肉目、鱗甲目、奇蹄目、鯨偶蹄目らと共に ユーラシア大陸起源とされるローラシアテリアと言うグループに分類されるなかで、 最も早く分岐したと確実視されているのが真無盲腸目である。 このグループはかつて、現在ではアフリカ獣類とされる様々な食虫性の小型哺乳類をほぼ全て網羅する分類であったが、 それはおろかなにんげんどもがまだ見た目や習性で動物を大別していた事に起因する誤りであった。 技術が発展し、分子系統解析で進化の道筋がDNAレベルで理解されると、 おろかなにんげんどもは収斂進化のまやかしを見破れるようになり、様々な分類が訂正されつつある。 モグラ科はそんなかつては分類の屑籠であった真無盲腸目の代表的な動物であり、 地中適応が著しい事で知られているぞよね。  モグラは日本全域で普通に見られる動物で、それらは全て日本固有種であるぞよ。 このフィギュアは所謂普通のモグラであるアズマモグラ、あるいはコウベモグラあたりがモチーフであろうが、 ま、日本のモグラなんてみんな似たような姿をするもんだ。 体長は12~15センチくらいで、尻尾は短め。 普段は地下にトンネルを掘って昆虫など食って暮らしているが、そんな生活が祟って弱視であるぞよ。 よく畑の芋や根を齧って悪さをすると言われる事もあるが、モグラってあんまりそう言うものは食わんみたいぞよね。 大体の場合、ネズミや虫が食ったのをモグラのせいにされているのだ。 しかし、そのネズミどもがどこからやってくるかと言うと、モグラの掘ったトンネルを利用して地下を跋扈する。 また、このトンネルそのものが悪さをして植物の生育を阻害したり、地盤を緩くしたりもするから、 そういう意味ではモグラも害獣と言っても良いだろう。  続いてこっちは「ホシバナモグラ」ぞよ! アメリカの北東部やカナダ東部の湿地に生息する半水生の珍しいモグラで、 最大の特徴は星とも花ともつかない奇天烈なシルエットのお鼻・・・! モグラは目が退化している代わりにアイマー器官が発達している。 吻の先端に微細なつづみ型の器官が密集し、これが多数の神経細胞に繋がっている為に、 触れるものを敏感に察知し、周囲の様子を感知できるのだ。 ホシバナモグラの場合はこのアイマー器官が非常に発達しており、22本もの突起が飛び出して異形を成す。 これが目にも劣らぬ高感度センサーの役割を果たし、 ホシバナモグラは土中のみならず水中にも餌を求める事が可能となったのだ。  モグラと言えば、アニメやゲームのキャラクターのモチーフとしても親しまれるぞよね。 よくモグラのキャラはサングラスをかけているが、上述の通り目が退化している為、そもそも光を感じる力が弱い。 つまり、モグラにサングラスは本当は必要ないぞよ。 あんまり眩しいと弱って死んでしまうとか言われる事もあるが、これもウソって事だ。 しかし退化していると言っても、すっかり目が無くなってしまったわけではなく、 全てのモグラは目を持っている。 あくまで見る力が弱く、視覚にあまり頼らない生物と言うだけぞよ。  おろかなにんげんどもってモグラ見た事あるぞよか? モグラは割に身近に存在する動物であるぞよ。 わたくしの住んでいる土地の周辺も、昔はまだ未開拓で畑やら空き地やら沢山あった。 時々土が盛り上がっている不思議があって、それはやはりモグラの作ったトンネルの痕跡なのだ。 幼少の頃、何度かうっかり外界に現れてちょろちょろしているモグラをわたくしも見たことがあるぞよ! しかしほんと稀な事で、人生でほんの数回と言った程度だろう・・・。 モグラは身近にいるが、地下ぐらしなので普段目につかない生き物なのである。 そんな街も近年はすっかり整備され、モグラのいるような土の緩い場所も無くなったかに思えるが、 どちらかと言うとわたくしが出不精になったから遭遇しないだけで、ほんとはまだそこらにいるのかもしれないぞよ。  モグラとホシバナモグラ、共通パーツからなるリデコ造形なので並べてみるとわかりやすい! 単なる使いまわしと思うなかれ、思ったより別パーツ化されていて凝ったバリエーションだ。  最大の特徴であるアイマー器官を有する鼻先は当然別造形。 ホシバナモグラは足に鱗状のプリントが施されており、これもモチーフの特徴を良く捉えた模様であるぞよ。 また、ホシバナモグラは水を蹴って泳ぐためか、モグラよりも後ろ足が大きい。 ここもそれぞれ別パーツが使用されている。  そしてモグラは尻尾がごく短いのも特徴だ。 ホシバナモグラは割に長めでシルエットが大きく変わっている。  モグラお尻。 胴体は共通パーツだろう。 しかし体色は異なっており、モグラの方がやや明るめ。 とは言え肉眼では殆ど判らんぞよ。  「あそべる生物フィギュア」はその名の通り、各部可動のアクションフィギュア! モグラは四肢がボールジョイント可動する他、首がスイング、尾もロールで僅かに向きを変える事が出来るぞよ!  くり抜き頭部が回転する事でシルエットを崩さず左右に首を振れるのはなかなか面白い構造ぞよね!  全く同じ構造なのでホシバナモグラも同様のポージング遊びが可能である。  デフォルメされたキャラクターとしてのモグラでなく、リアルなモグラ! なかでもホシバナモグラなどは稀な立体化と言えるだろう・・・! モグラファン垂涎のアイテムぞよーっ!!  続いてこちらは「ブロブフィッシュ」ぞよ! これはインターネットの大好きなおろかなにんげんどもなら見たことがあるんじゃないぞよかな? 任天堂のゲーム「MOTHER2」よりシリーズに登場する知的生命体 「どせいさん」そっくりな深海魚として話題になる事のあるアレだ!  ぶよぶよピンクのどせいさん深海魚・ブロブフィッシュは、世界で最もぶさいくな生物としても知られるぞよ。 しかし、これ程不名誉で不本意な称号はあるまいと本人は思っているに違いない・・・! なぜならブロブフィッシュとはこの深海魚本来の姿では無いからだ! 我々がブロブフィッシュと呼ぶこの魚の正体はウラナイカジカ属の深海魚9種、 いずれかの死体であるぞよ・・・! 本商品では「ニュウドウカジカ」がモチーフとなっているみたいぞよね。  ニュウドウカジカは本来、水深480~2800メートルの海底から離れずに棲む底生の大人しい深海魚であるぞよ。 北海道オホーツク海・太平洋沿岸や東北日本海などでもしばしば揚がる事があると言う。 元々の生息域ではこのようなドロドロに溶けた姿はしておらず、 分厚い唇は特徴的だが割に精悍な見た目をして、 黒褐色の体表にちくちくと棘が見られるのは、これがカサゴの仲間であるからだろう! 海は10メートル潜るごとに1気圧の水圧が常にかかる過酷な世界である。 この水圧と言うのは当然ですが、海中の物体に全方向から均等にかかっているぞよ。 おろかなにんげんどもなどがうっかり何の対策もせずに深海へ生身で赴くと、 体中に圧力がかかり、特に肺など空気を含む内臓はぺしゃんこになって大変な事になってしまう。 一方で深海魚はそんな水圧の当たり前な世界で生きているので、体の構造からして深海に適応しているぞよ。 普通魚は体内に浮袋を持って浮力を得ているが、中身が空気では深海でぺしゃんこになって死んでしまう。 それだから深海魚は気圧の影響を受けにくい油脂やガスで浮袋を満たしたり、あるいは退化させたりと工夫する。 そして体を構成する細胞にも工夫があり、ゼラチンのようなぷるぷるの構造を取り、 水圧で割れてしまいがちな鱗を持たない選択をするなど様々な方法で深海に体を適応させているのだ。  ニュウドウカジカはまさに水圧に耐える為に浮袋を退化させた種の深海魚であるぞよ。 体は水分と脂肪を多く含むゼラチン質で構成されているが為に、 周囲の海水よりも僅かに比重が小さく、海底近くで浮力を得る事が出来ている。 そんなニュウドウカジカが時折おろかなにんげんどもに釣られたり、底引き網で水揚げされたりするとどうなるか。 これまで体にかかっていた水圧が急激に消失するので、 ゼラチン質の体が膨張し、皮膚が剥がれてピンクの肉が露出。 全体にドロドロに溶けた醜い姿に変わってしまうのである・・・! そう、ブロブフィッシュとは哀れな深海魚が急に地上に引き上げられた事で天に召された姿だったのだ・・・!  って事で本商品は「あそべる生物フィギュア」史上でも稀な「死体」のフィギュアなのである・・・! このような深海性の魚の本来の姿・生態は、生息域が到達困難なだけにまだまだ未知の事だらけ。 しかし、ニュウドウカジカは日本の水族館でも比較的長期にわたって展示される事があり、 名誉回復も進んでいるぞよ。 また、存在が知られた事でこいつを食ってやろうと勇むおろかなにんげんどもも増えており、 近年では珍味として食される事もあると言う。 水分量が非常に多い魚なので身・骨共にぷるぷるで柔らかく、意外と良いおダシが出るそうな。  そんな哀れなる末路・ブロブフィッシュを、本商品では光沢のあるピンクの質感で再現。 どせいさんみたいな飛び出た特徴的な鼻が再現されている。  お腹側はあっさり目。 ぶよぶよなので平らな所に置くと潰れちゃうのだ。  一応あそべる~シリーズなので一部可動フィギュア仕様! ヒレと尾がスイングします。 ・・・死体だけどな!!  短いヒレを振る姿が哀れにも愛らしいぞよ。 こちらも世にも珍しいリアル造形立体化・・・ キャラクターナイズされた姿でなく、リアルなビジュアルでちびっ子向け玩具になるのは初なのではないか? 貴重ぞよ!!  そしてラストは・・・なんとまさか! 「チンパンジー」ぞよ!!   なぜこのラインナップで最後がチンパンジー・・・!? モグラは地下に、ブロブフィッシュは深海に棲むので視力に依存しない生活をしている点で共通点がありそうだが、 チンパンジーは関連性がさっぱりわからんぞよ! タカトミアーツのチョイスはかなり通なので、わたくしの気づかん共通点があるのかも・・・?  チンパンジーはユーアーコンタグリレスと言うグループに属する霊長目の哺乳類であるぞよ。 このグループは鎖骨が発達しており、古くから森林や樹上生活が長い事が示されている。 モグラの属するローラシアテリアとはまた別のグループだが、どちらもより広い分け方では北方真獣類に属している。 北方真獣類を大きく二分すると、ユーアーコンタグリレスとローラシアテリアに分けられると言う事ぞよね。 モグラもチンパンジーも、哺乳類の分類を研究する上では重要かつ研究者に人気のある動物であるぞよ。 今回のラインナップは双方の代表と捉える事が出来るかもしれない。  霊長目と言うのは君達おろかなにんげんどもを含む、サルの仲間であるぞよ。 中でもチンパンジーはとりわけ人に近い存在と言われ、 DNAの塩基配列98.8%がヒトと同じである事が解っている。 チンパンジーは群れを作る社会的な動物で、群れ同士はいつもいがみ合い、殺し合っているぞよ。 おろかなにんげんどももまた、この令和の世になっても飽きもせず戦争で多民族を殺しまくっているが、 これは遺伝子の本能に刻まれた習性であるからして、仕方のない事なのです。 日本などは侵略の難しい島国でほんと良かったぞよ!!  トップ。 全く関係ないのだが、その昔Windowsで「ジャングルパーク」って言うゲームが出ていてさ~。 主人公のサル(SARU)を操作して遊園地や公園のあるマップをただ散歩するだけって言うヤツなのだが、 遊んだことあるおろかなにんげんどもいるぞよか? 面白いかって言われると別になんも面白くないのだが、わたくしは雰囲気が結構好きだったぞよ。 未だに特典キーホルダー付きのパッケージ持ってるしね。  ボトム。 チンパンジーは樹上性なので、足の指は親指が特に離れ、木を掴むのに適した形をしているぞよ。  あそべる生物~は各部可動の簡易アクションフィギュア! チンパンジーは各関節がスイングし大きく表情を変える事が出来るぞよ。  立ち上がりポーズから、こんな風にナックルウォーク姿勢へ変更も出来る。  勿論手持ちの枝は着脱可能。 チンパンジーは非常に知能が高く、日常的に道具を用いる事でも知られるぞよ。 このような木の棒などを巣に差し込んでエサとなる生き物を釣ったりするのだ。 こうした行動は群れごとに継承されており、チンパンジーが文化を持つ事の証であるとも言われている。  タカラトミーアーツの「あそべる生物フィギュア」はガチャガチャ売り場でゲットできるジェネリックアニア的側面も持つ! 本家アニアと組み合わせて世界観を広げよう!!  ネズミとは申せ、実はハリネズミもまたモグラと同じ真無盲腸目の哺乳類であるぞよ。 見た目は全然違うようでいて、長い吻やトンネル状の巣穴を掘る事など共通点もあるのだ。  「あそべる生物~」の霊長類と言えば、 2023年発売の「猿たちの楽園」でゴリラとショウガラゴがラインナップされていた。 わたくしは霊長類はどうも野蛮で暴力的なおろかなにんげんどもを連想して好かんのだが・・・ このショウガラゴちゃんはおめめがでっかく愛らしい姿をするので気に入っているぞよ。  そしてチンパンジーは既に廃番となっているが、「AS-14 チンパンジー(2018)」としてアニアにラインナップもされていた! 比べてみると・・・「あそべる~」の方がディテールが細かく頭部や肘可動も設けられており、さらにでかい・・・! 後発なだけあってよく出来ているぞよね! もっとも、耐久性に乏しいこのような肘可動はガチャフィギュアならではで、 安全基準高めなアニアではまず採用できない構造であるから、一概にどっちが良い出来とも比べられんぞよ。 また、チンパンジーに関しては上記アニアレビューも参照のことぞ!  広がるおさるワールド! 積極的に集めている訳ではないがだんだん霊長類も集まってきたぞ・・・!  深海生物にはブロブフィッシュが仲間入り・・・ が、こいつ死体ぞよよよよ・・・。  海底を這うニュウドウカジカを発見! これより捕獲を試みる・・・!  急速浮上により皮膚が裂け身体が崩壊してしまうとはなんと恐ろしい所業・・・! おろかなにんげんどもも現世で徳を積まないと来世はブロブフィッシュに転生してしまうかもしれませんよ。  共通点があるようなないような・・・ 奇怪な生物達がラインナップされた2024年11月弾「いきものフシギ大列伝」でした! シリーズでも類を見ない地味で目新しい面々・・・特にブロブフィッシュは是非入手して欲しいレアな一品となっている! おろかなにんげんどもよ・・・今月もガチャ売り場へ走れ!!  「ばらむツZ」の哺乳類展レポを読んで生物への理解を深めよう・・・! :このリンクを踏んで何かポチるとわたくしにささやかな報酬が入りサイトの運営費となるのでよろしくぞ! ・「ハセガワ 1/72 しんかい 6500 プラモデル」 ・「お風呂で遊べる入浴剤 38SERIES ゆるかわ深海魚ハンター」 ▲TOP |
■タカラトミーアーツ あそべる生物フィギュアシリーズ 深海のひみつ 巨大クジラ VS 巨大イカ  タカトミアーツより、2024年10月発売の一回300円ガチャ! ちびっ子に大人気の「あそべる生物フィギュアシリーズ」のうち、 深海にフォーカスした「深海のひみつ」第4弾となっている!  この深海シリーズは2021年に登場してから毎年秋~冬になってくると新弾が出ているぞよ。 今回は2021年の第一弾「深海のひみつ」からダイオウイカが、 2022年の「DEEP ADVENTURE」からマッコウクジラがカラバリ再録されています。 ラインナップはマッコウクジラが3色、ダイオウイカが2色封入の全5種類。 激しいバトルで傷ついた「激闘ver」が登場し、目玉となっているぞよ。 わたくしは過去弾でマッコウクジラとダイオウイカを入手しそびれていたので嬉しい再録弾となった!!  それでは中身を見ていこう! こちらは「マッコウクジラ」の通常カラー。 ひょっとしたら細部彩色が変わっているかもしれませんが・・・2022年登場時と同じカラー・プリントかな? 全長15センチのビッグサイズフィギュアぞよ!  マッコウクジラは北極から南極まで、世界の深海沖に広く分布する鯨偶蹄目のハクジラであるぞよ! 大きく肥大化し、四角張った頭が特徴的で、 顎に歯を持つタイプのハクジラの中では最大種・・・つまり歯のある動物では世界最大級である! そんなマッコウクジラの全長はオスでは最大で18メートルにもなるが、メスでは13メートル程度。 オスの体重50トンに対しメスは25トンと、全ての鯨類の中でも性差が大きい事が特徴であるぞよ。 社会性が強い事でも知られ、家族の繋がりを大事にする動物でもあるぞよ。 群れは母系中心でメスとその子供からなり、時に40~50頭もの大群になると言う。 そんな群れの中で、お母さんクジラは子クジラの泳ぎが上達するまで甲斐甲斐しく世話をするぞよ。 オスのマッコウクジラは10歳くらいになると自立心が芽生え、出自群を出奔。 似たようなオスの仲間と群れを作り、温かな海域に留まるメスの群れから離れて、寒冷な地域で生活をし出す。 そうして18歳前後で性成熟を迎えるとオスはメスの元に戻ってきて、他のオスと争うように複数のメスと交尾をしだすぞよ。 メスは9歳ほどで性成熟を迎えると言うから、女の子の方が早熟である。 出産に際してはお母さんクジラと子クジラを守るように他のクジラ達が盾となると言うから、健気にも優しい動物であるぞよ。  現生のクジラは二種類いて、ハクジラ類とヒゲクジラ類に大別できるぞよ。 ハクジラはその名の通り歯を持つ鯨類。 ヒゲクジラは歯を持たず、上顎から生えたひげを使ってオキアミやプランクトンなどをこしとって食う種であるぞよ。 大量の海水を口に含み、一度に獲物を吸い込む都合か、ヒゲクジラは全体に大型化する傾向にある。 一方でハクジラ類は頭部にメロンと言う脂肪組織の塊を持ち、 これを用いた超音波の発声で周囲を探ったり、仲間と交信したりする特徴を持つ。 この能力を反響定位、エコーロケーションと言うぞよ。 マッコウクジラも互いに音を発してコミュニケーションを取っており、 それぞれの群れには独自の方言の様なものすらあると言われている。  マッコウクジラはおろかなにんげんどもとも関わりが深い動物でもある。 そも名前の「マッコウ」とは抹香、典雅なる香りのする香の事であるぞよ。 その昔、浜辺には龍涎香という世にも香しいにおいを放つ不思議な石が打ち上げられる事があった。 おろかなにんげんどもはこれを龍の唾液が固まったものであると捉え、宝物としたぞよ。 しかし、おろかなにんげんどもが捕鯨を覚え、マッコウクジラを捕らえる事が可能になると、 この正体が判明した。 龍涎香はマッコウクジラの腸内で稀に形成される結石であったのだ。 マッコウクジラはおろかなにんげんどもに様々利用される。 頭部のメロンの中には鯨蝋と呼ばれる脳油が溜まっていて、これは蝋燭やせっけんの原料となり、 燃料としても利用された。 大量のお肉は食用として重宝するぞよ。 そして体内から運良く龍涎香が出てくれば一攫千金ぞ! こうしてマッコウクジラと海の男達のそれはアツく苛烈な戦いが始まったが、 マッコウクジラも負けてはいない。 マッコウクジラは鯨の中でも獰猛で、おろかなにんげんどもを超絶パワーで船ごと撃沈しては深海に去ってゆくのである・・・。 超巨大海生哺乳類であるマッコウクジラにとって、したがっておろかなにんげんどもは天敵であるぞよ。 海の中にいる天敵は、他にシャチがいる。 同じ鯨類であるが、獰猛なハンターとして知られるシャチはいつもマッコウクジラの子供を食おうと狙っているぞよ。 前述の通り、メスと子からなるマッコウクジラの群れは、屈強なシャチ達にとって入れ食いサービスなのである。 哀れ、シャチの群れに襲われて子を食われるマッコウクジラ・・・かと思った次の瞬間! どこからともなくオス達が駆けつけ、メスと子を救って去ってゆく・・・ こういうカッコイイ場面も海ではしばしば見られると言う。 そして、シャチは深く潜る事が出来ない為に、深海へ逃げ切ればマッコウクジラの勝ちと言うワケだ。  そんな過酷な海で日夜戦いに明け暮れるマッコウクジラは、歴戦のものほど古傷を増やしてゆく・・・。 それを再現したカラバリこそ、この「激闘ver」である・・・ッ!! 頭部のでっぱったマッコウクジラは天敵を退ける時や、仲間同士での争いにおいても額が傷つきやすい。 この激闘verではそんな頭部の傷をプリントで再現していると言うワケぞ。  原型は通常verと共通で、 明るめの体色に傷痕プリントはキャラクター感が強調されており、アニメチックであるぞよ。 この傷痕の形、実はある動物につけられた跡であるのだが・・・後述ぞ!  三つ目のカラバリはこちらの「白鯨」verだ! 生き物が普通と違う白い姿になる仕組みにアルビノがある。 これは色素欠乏による先天性の疾患で、色が抜けて体色が白くなると共に、視力の低下など様々な不具合が生じるものであるぞよ。 一方、遺伝子は正常ながら色素が減少してやはり体色の白くなるものも、動物には稀に生まれてくるぞよ。 こうした先天性の変異を白変種という。 そも動物は体色を白くする事で雪や光に紛れ、様々な場面を有利に生き残ってきた。 このような白化の遺伝情報は動物の中に脈々と受け継がれており、 それが時たま表に出てきた時に白変種個体として生まれつくのである。 体色の白いクジラは白鯨と呼ばれ、おろかなにんげんどもの関心を引くが、 アルビノや白変種など、何れにしても先天的にこのように生れつくものであるぞよ。  世界で最も有名な白鯨に、19世紀前期に太平洋で鯨捕り達と激しく戦った歴戦の勇士、モカ・ディックがいるぞよ。 モカ・ディックはそれは巨大で力強いオスのマッコウクジラで、 伝説によれば鯨捕り達と100度戦い、時に仲間を救い、時に捕鯨船を撃沈し、生き残ってきたと言われるぞよ! このモカ・ディックがどうして白い姿をしていたのかは謎に包まれているが、 なんでもアルビノや白変種ではなく、歴戦の古傷が無数に体へ刻まれているが為に白く見えたとも言われている。 当時の海では悪魔の様な狂暴な白鯨として恐れられたが、 それはおろかなにんげんどもが欲の為にマッコウクジラを殺めるので、捕鯨船に反撃していた為であり、 平時は温厚でしばしばおろかなにんげんどもの船に興味を示し、傍に寄って遊ぶ無邪気な性質であったと言われるぞよ。 クジラは音を聴くので、きっと捕鯨船とそれ以外の船との区別もついたのだろう。 これをして悪魔と言うのは、全くおろかなにんげんどもは高慢で自惚れが過ぎると言うものぞ。 そんなモカ・ディックが遂に打ち取られたのは1838年の事。 おろかなにんげんどもに殺されそうになった子クジラを助けに現れた所を捕殺されたと言う事である。 その巨体からは100バレルの鯨油と数多の龍涎香が得られ、実在の白鯨伝説として現代にも伝わっているぞよ。  そんな白鯨はしばしば物語のモチーフにも使われる! 最も有名なものでは、このモカ・ディックをモデルとした、 白鯨モビィ・ディックとエイハブ船長の漢の戦いを描いた「白鯨」があるぞよね! そしてこのモチーフは不思議と宇宙と関連付けられる事も多く、宇宙鯨の登場する作品も数多あり、 特にアニメでは宇宙鯨のリーダーが白鯨である事が多い印象ぞよ。 わたくしの大好きなアニメ「マクロスダイナマイト7」でも、宇宙を回遊する植物性のエネルギー体が銀河クジラと呼ばれて、 「白鯨」がモチーフのドラマが展開されていた。  この白鯨バージョンなんですけど、単なる白カラーかと思いきや成型色がほんのり薄ピンクで実に生物っぽい色味をしているのだ! 表面は白で塗装されているのかな? 透け感があって雰囲気出てるぞよ!!  生き物と言うのは、大体左右対称の姿をしているぞよ。 もともと生物はこのような構造を持っていなかったが、約5億5000万年前に起こったカンブリア紀の大爆発によって、 左右対称の生物が一気に世界に跳梁するようになった。 とは言え、体の内部構造は非対称である事が多く、内臓がどっちかに寄っていたり、様々であるぞよ。 このマッコウクジラは鯨類の中でも奇妙な外見的特徴を持ち、頭部が左右非対称なのだ! 正面から見ると鼻の穴にあたる噴気孔が左側にある特徴が、 本商品でもばっちり再現されているのがわかるぞよね! なんでもこのような左右非対称の構造を持つ事で、より反響音を立体的に捉える機能が向上すると言う。 つまり、エコーロケーションの為に進化した身体構造と言う事ぞよね! マッコウクジラは目に見えて極端だが、ハクジラ類は全体にこのような左右非対称の頭骨を持つぞよ。  通常カラー、激闘ver、そして白鯨。 この弾だけで3種のカラバリがゲットできるぞよ。 単なる色違いでなく、コンセプト違いなのがちょっと嬉しい。 これは集めたくなるカラバリぞよね!  わたくしはてっきり激闘verと白鯨が目玉に思っていたが、 通常カラーはボディ下部から尾鰭にかけてまでプリント箇所が多く、最も豪華な仕様。 こりゃあハズレ無しと言って良いだろう!!  本弾には「ダイオウイカ」もラインナップされているぞよ。 こちらもご存知、深海生物では良く知られた巨大生物ぞよね!  2021年に初登場した際は全身オレンジのグラデ塗装が施されていたが、 2022年の再登場から細かい彩色が省略されている。 今回はより白っぽい体色の新たなカラバリぞよ。  ダイオウイカにも「激闘ver」があり、胴体に傷痕がプリントされたバリエーションとなっている。  原型は共通で全長約18センチの超ビッグサイズフィギュアとなっているぞよ。  世界最大級の無脊椎動物にして、最大級の頭足類として知られるダイオウイカは、 胴体部分の体長が13メートル以上にもなる化け物の様な巨大イカであるぞよ・・・! それに加え、時に10メートル近くにもなる触腕が二本伸びているのだから最早怪獣である。 このような深海性のイカは体にアンモニアを含む事で浮力を得ているぞよ。 巨体の重さを水中でゼロに近づける事でエネルギー消費を抑えているというワケぞ! 世界中の温暖海域から亜寒帯海域に広く分布し、水深650~900メートルの中深層を主な狩場とし、生活しているが、 深い海の事・・・その生体はまだまだ謎に包まれているぞよ!!  ダイオウイカは普通、生きている時は赤っぽい色をしている。 太陽の光は水深が増す程に水中に吸収され消失していくが、 水深200メートル~1000メートルの上部漸深海帯では僅かに明るさが残っているぞよ。 光の波長は赤い波長から先に吸収されてゆくので、赤い動物は黒っぽく見えて目立たない。 これが為に、深海生物は赤っぽい姿を取る事も多いのだ。 ダイオウイカが赤いのはこういう理由があるぞよ。 それが死んで打ち上げられると表皮が剥げて白っぽくなってしまう。 本商品は白っぽい姿なので、どっちかと言うと活きの悪い死にかけのダイオウイカって事になるかもしれないぞよね。  同じく巨大イカであるダイオウホウズキイカが触腕にカギ爪を持つのに対し、ダイオウイカは歯の生えた吸盤を備えている。 10本ある足のうち、特に長い2本の触腕で獲物に接触し、 他のイカや深海魚を捕らえて食うと言われているぞよ。  世界の海に広く住まうダイオウイカであるから、日本近海でもしばしば見られる。 しかし10メートル級とはならず、最大でも5メートル前後のものが多いみたいぞよ。 イカと言うと日本の食卓にも普通に並ぶ食材でもあるぞよね。 こんなに巨大なイカなら食い放題だと思うなかれ、前述の通りダイオウイカはアンモニアを多く含む為にどう考えてもマズそうだ。  「あそべる生物フィギュア」はその名の通り、動かして遊ぶ事の出来る簡易可動フィギュアである! マッコウクジラは口が開閉し、体が一か所スイングして表情付けが可能ぞよ。  大海を優雅に泳ぐマッコウクジラが再現できるのだ・・・! 遊泳ポーズでの展示には汎用スタンドが欲しいところ。  簡易可動だがなかなかそれっぽい表情付けが可能ぞよね!  ちなみに口内の色もそれぞれのカラーで別ものぞよ。 通常カラーは白彩色、激闘Verは無彩色、白鯨verはピンクで彩色されている。  ダイオウイカは足が二本ずつ展開可能。 更に触腕は付け根でロールできるので、うねりの向きを少しだけ変更する事が出来る。  八本の足が外側に大きく開くので、シルエットをがらっと変える事ができるぞよ!  こちらは様々なフィギュアと組み合わせて遊ぶのに重宝しそうな可動である。  白鯨に率いられたマッコウクジラの群れが出現ッ!! 大海を優雅に泳ぐ、地球史上最大級の動物群ぞよ!!  この弾だけで3色のマッコウクジラがラインナップされているので、 並べるだけでも賑やかで目にも楽しい。 マッコウクジラは群れで生活する社会性のある動物なので、 ダブっちゃっても並べて飾れるのが嬉しいところ。  マッコウクジラは疲れると丸太のように腹ばいになって水面に浮かんで休む癖がある。 時に頭を上向きや下向きでぷかーっと浮かぶ事もあり、これは眠っている時と考えられるぞよ。 マッコウクジラがこうして無防備に睡眠をとる時間は、1日のわずか7パーセントの割合とも言われ、 陸生哺乳類に比べると常に活動している事がわかっている。  マッコウクジラの群れが何かを発見したぞよ! あれは・・・ダイオウイカだっ!! なにせ巨大な動物かつ深海域で活動する為、両者の生態は判っていない事が多い。 しかしマッコウクジラは深海へ潜った後、ダッシュ&急旋回で活発な活動を取る姿が確認されている。 これはつまり、何か獲物を積極的に襲って食っている姿だと考えられるぞよ。 ダイオウイカなどはまさにその獲物の一つであると言われている!  マッコウクジラを解剖すると、かなりの確率で胃からダイオウイカの死骸が出てくる事があるぞよ。 マッコウクジラにとって深海を漂うダイオウイカは格好のご馳走であり、 ダイオウイカにとってはマッコウクジラは天敵であると言う事だ! 両者は時に深海で激闘を繰り広げていると言われるが、 光の届かず、また水圧のかかる深海ではこの様子を観察する事もままならない。 マッコウクジラとダイオウイカの戦う姿は、まだ誰も見たことがない伝説の戦いぞよ。  しかし、マッコウクジラとダイオウイカが戦っている事は確実ぞよ。 なぜならマッコウクジラの頭に、時折ダイオウイカが抵抗したと思われる吸盤の痕が見つかる事があるからだ。 前述の通り、ダイオウイカの吸盤には歯のような構造があり、巻き付かれると傷痕が残る。 マッコウクジラの大好物としてはやはり巨大イカのダイオウホウズキイカもいるが、 こちらの触腕には爪が生えていて、ダイオウイカの触腕とは構造が少し異なるぞよ。 ダイオウイカに巻き付かれると吸盤の傷痕がつき、 ダイオウホウズキイカに巻き付かれるとカギ爪の痕が残るワケぞよね。 この傷痕の違いで、そのマッコウクジラがどの辺りの海を餌場としているかを推理する事も出来ると言う。 本商品のマッコウクジラ激闘verは、まさにその吸盤の痕がプリントで再現されている・・・! 即ち、ダイオウイカと争った証拠であるぞよ!! そしてダイオウイカ激闘verの傷痕は、恐らくマッコウクジラに齧られた痕であろう・・・!! 両者を組み合わせる事で伝説のバトルが再現できる・・・ まさに「激闘ver」なのだ・・・!!  しかし激闘とは申せ、ダイオウイカの触腕にクジラをどうにかするパワーがあるとは到底思えん! 大体の場合齧られるだけ齧られ放題に違いないぞよ・・・! ま~中にはどんくさいマッコウクジラもいて、 イカに絡みつかれてうっかりこんがらがり、そのうち窒息死してしまう者もいるかもしれんが・・・稀な事であろう。  しんかい6500発進ッ! わたくし潜水艦部隊と共に、深海探検に出発ぞよ!!  なんと巨大なダイオウイカだ! 深海性の動物では目が退化している者も多くいるが、ダイオウイカの場合最大で直径50センチにもなる巨大な目を備えている! これは全ての動物の中でも最も大きいとされる目玉であるぞよ・・・! こんな目に深海で遭遇したら・・・恐ろしすぎて気絶してしまうかもしれんぞよよよよ~っ!! これは深海で光をより多く取り入れる為の巨大化であると考えられた事もあったが、 実は目玉がどれだけ大きくても、極端に能力が向上する事はない。 それよりも水の光学的性質が邪魔をして、深海での視力には限界が生じる為であるぞよ。 しかし、これ程巨大な目玉を備える事は、生物にとってそれだけ負担であり、コストであるからして、 巨大化には必ず理由があるのだ。 実は巨大イカの特大サイズの目は、近くを見る能力に乏しい一方、極度の遠視であると言う。 これが遠くの天敵の動きを察知するのに役立つのだ! ダイオウイカの天敵・・・すなわちマッコウクジラが水中を移動すると、 微小な発光生物らが水流で暴れ、ほんのかすかな軌跡を描く。 ダイオウイカの巨大な目玉は、この微生物の放つごくわずかな光を捉え、遠方の危機を察知するのである・・・! ダイオウイカの巨大な目玉は、マッコウクジラに対抗する為の防衛策と言うワケぞよ!  しまった! ダイオウイカに捕まってしまった!! 危うし、探検隊・・・ッ!!  そこへ駆けつけてくれたのはマッコウクジラの群れだ! ほんの気まぐれだろうが、わたくし達を助けてくれたに違いないぞよ・・・!!  おっと、この傷つき弱ったダイオウイカは捕獲し連れて帰るぞよ! 深海性の珍しい動物を研究する事で、思いがけない発見があるかもしれん!  ざぱーんっ! 水上に出ても抵抗する巨大イカ!! おろかなにんげんどもが海に進出した頃、漠然とした大海への恐怖を悪魔の如き生物に置き換えて恐れ、また実在を信じた。 無数の足を持つ巨大な怪獣・クラーケンもまたその一つであるぞよ。 古くはオオダコの姿で描かれ、時に船を引きずり込み沈没させたと言うが、 これが実在し、その正体こそダイオウイカではないかとする説も根強い。 もっとも、ダイオウイカはこんな風に海からざぱーんと現れて船を食ったりはしないだろうが・・・。 この玩具も、船の模型と組み合わせて遊んでも楽しいかもしれないぞよね!  深海は古くから人々の関心を引く未知のエリアであり、 今尚未踏の地であり続ける神秘の領域なのである・・・!  だんだん増えてきた鯨類のフィギュア。 あそべる生物はガチャ売り場で買えるジェネリックアニア的存在として、 本家タカトミシリーズの拡張アイテム的側面もわたくしは感じてるぞよ。  クジラはユーラシア大陸が起源と考えられるローラシアテリアの哺乳類で、 鯨偶蹄目に分類されている。 近年の分子系統学解析によって、鯨類とカバが近縁である事がわかり、新たにこのグループに統合されたのだ。 首の長いキリンさんや、より原始的なオカピなどもまたこのグループに含まれる親戚ぞよ! クジラとカバが近縁とは驚きであるが、そう言われてみるとカバも水中生活に適応した哺乳類だ。 そんなカバのより原始的な姿とも言われるコビトカバは陸地に住まうが、やはり水遊びは大好きで、 動物園だと水の中に潜っている事も多い。 遥か太古にも、このように水遊びの大好きな哺乳類がいて、 やがて海で住まう事を覚え、完全な海中生活に適応し、鯨類へと進化したのだ・・・! 生命の神秘であるぞよ~っ!!  2造形×カラバリの全5種がラインナップされた「深海のひみつ 巨大クジラ VS 巨大イカ」! 15センチのマッコウクジラに、ダイオウイカは全長18センチ級とおよそガチャとは思えんボリューム感だが、 全種集めても1500円と言うのは良心的に過ぎる・・・! タカトミアーツって慈善事業なのかーっ!? クジラとイカならいくつあっても良いし、回しやすい弾ぞよね! おすすめぞーっ!!  海に住まうクジラも元々は地上に生まれた哺乳類であった。 「ばらむツZ」8巻の哺乳類特集で生き物にちょっぴり詳しくなろう!! :このリンクを踏んで何かポチるとわたくしにささやかな報酬が入りサイトの運営費となるのでよろしくぞ! ・「フェバリット マッコウクジラ FM904」 ・「カロラータ ダイオウイカ ぬいぐるみ」 ▲TOP |
| ▲TOP |
| ■ |